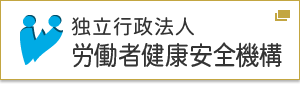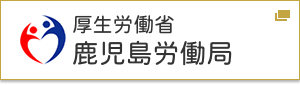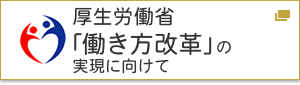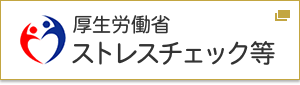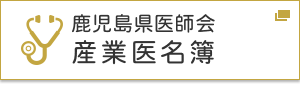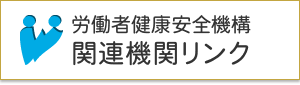令和7年12月
「産業医としての学び、弾丸セミナー」
中島 一壽
(鹿児島地域産業保健センター 登録産業医)
鹿児島市で産業医として活動しています。私は研修医の頃、産業医科大学で集中研修を受け、産業医の資格を取得しました。現在は、行政関係、市内の医療法人、そして電子部品製造工場で嘱託産業医を務めています。主な活動は、衛生委員会への出席、職場巡視、長時間労働や高ストレス者への面談、健康相談などです。日々、職場の皆さんが安心して働ける環境づくりを目指しています。
産業医の業務は、法令遵守や健康管理だけでなく、働く人の「こころ」と「からだ」の両面を支えることが求められます。そのためには、現場での実践だけでなく、常に新しい情報や考え方を学び続けることが大切です。私は産業医としての知識や視野を広げるために、産業医科大学が主催する「プレミアムセミナー」に2回参加したことがあります。これは全国から産業医が集まり、泊まり込みで議論や研修を行う、いわば“弾丸セミナー”のような企画です。
セミナーでは、有名企業や省庁で産業医をされている先生方と直接ディスカッションする機会があり、現場での共通の悩みや対応策を共有できたのがとても有意義でした。中でも印象的だったのは、夜に行われた懇親会です。名刺交換とビンゴゲームを掛け合わせた独自の企画で、25人の先生方と名刺を交換しながら5×5のマスにサインを集めていき、主催者が名前をコールしてビンゴを進めるという内容でした。自然と交流が生まれ、他の産業医の方々とのつながりが深まりました。こうした場で得られるネットワークは、日々の産業医活動にも大いに役立っています。
ちなみに、今年のプレミアムセミナーは12月13日・14日の土日に、東京・大井町のホテルで開催されるそうです。私は今年不参加ですが、有害業務管理や健康経営など、実務に役立つテーマが多く、興味深い内容が予定されています。参加される先生方にとっても、きっと有意義な時間になることでしょう。
今はインターネットを通じて、さまざまな情報を自分のペースで学ぶことができます。しかし、実際に産業医として活動している方々と顔を合わせ、同じ課題について語り合う経験は、何ものにも代えがたい学びになります。臨床を続けながら産業医の知識を深めたい方にも、こうした泊まり込みのセミナーへの参加をおすすめします。仲間とともに学ぶことで、より広い視点から「働く人を支える医療」を実践できるようになるはずです。
産業医だより 2025年12月