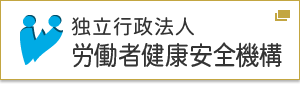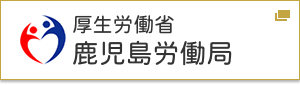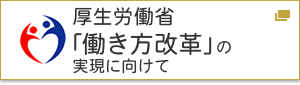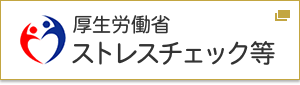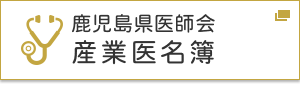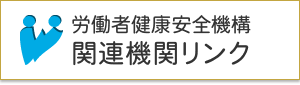メールレター 第261号
■■■sanpo■■■■■■■■■■■■■■■■■■
≪「さんぽ鹿児島」メールレター≫ 第261号(2024.12)
発行:鹿児島産業保健総合支援センター
所長 草野 健
■■■■■■■■■■■■■■■■kagoshima■■■
相談員からのメッセージ
仕事と通院の両立支援で企業の健康経営を目指せ
産業保健相談員 德永 龍子
(鹿児島純心大学名誉教授)
(担当分野:保健指導)
就労者6900万人のうち、がんや生活習慣病などで通院している人は2325万人に上り、全体に占める割合は40.6%と2001年28.2%から増加が続く(2022年厚生労働省の国民生活基礎調査)。
これは、医療技術の進歩で通院可能者増に加え、高齢就労者が900万人を越え就労者年齢が20年で4歳上がり、女性の就労を促す制度整備を通じて未受診率の高い女性の就労者の増加も背景にある。
一方、仕事と治療の両立支援は、育児や介護と異なり、ガイドラインの策定やがん対策基本法で触れられているものの企業側の責務を盛り込んだ法整備が進んでいない。
通院の病気は、高血圧症16.6%、糖尿病8.0%、歯の病気7.0%、腰痛症5.7%、脂質異常症5.4%、目の病気3.9%、うつ病などの心の病気3.6%である。食生活の変化や、長時間労働に伴うストレス、運動不足などの要因が指摘される。通院する人の割合は非正規就労者の方が多い。男性は正規が33%で非正規は51%である。女性は正規が34%で非正規42%である。仕事と通院の両立支援の職場の環境整備は、人材確保の観点から企業にとっても重要なテーマとなる。日本の勤務体制では持病をかかえて仕事を続ける事が困難である状況がある。両立支援の制度は整備されたが、通院している正規及び非正規就労者の対応に主治医や企業側が慣れていない職場や未だ制度の必要性に気づかず未整備の職場が混在する。
2022年労働政策研究・研修機構の調査では、病気後に同一勤務先で仕事継続者は74.6%だった。病気理由での退職者は7.6%であり、それ以外の理由退職者を合わせると4人に1人は病気後退職している。
通院する非正規就労者が多い一方で、企業のサポートは十分とは言えない実態もある。同上の調査では、病気休職制度の適応が非正規就労者には「ない」と答えた企業が全体の3割超に上った。時差出勤や在宅勤務の働き方は非正規就労者にも認められつつあるが、1割程度の企業ではまだ認められていない。
企業には、従業員の健康増進を経営的観点から考え戦略的に実践する「健康経営」がある。経済産業省では、3月大企業2,988社、中小企業16,733社を「健康経営優良法人2024」に認定した。優良法人の企業従業員数は、日本全体の約15%まで拡大してきた。その手法は、社長を含む経営会議等で経営として改善を継続する仕組みをつくり、従業員の理解を得て実施している。実施企業では、働き方改革とDXで労働時間を減らし、食事改善、運動、良質な睡眠の確保、仕事と通院の両立支援などで従業員の健康増進等企業なりの工夫がある。成果では、従業員の人材定着率や生産性が高く、高ストレス者の割合が低く、長く生き生きと働ける人が増え労働力不足を補い、企業価値の向上につながっている。
厚生労働省は、社員の健康増進を図る中小企業に補助金給付を新設した。先行事例や取組みがネットで紹介される。県別では鹿児島県は、281社0.61%で全国12位、鹿児島市は、143社50万~100万人の市では第3位である。
今以上に仕事と通院の両立支援の職場環境整備、労働者の健康の維持増進による人材確保で、企業の生産性向上を促進し健康経営優良法人を目指してほしい。
(日経新聞2024年3月28日、8月17日参考)
産業保健研修会のご案内(12~2月開催分 受付中!)
┏―[ 産業保健研修会の詳細・申込はこちらから ]―――――┓
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h2335
┗――――――――――――――――――――――――――――┛
当センター主催のセミナーのご案内(受付中!)
当センターでは産業保健研修会以外に、事業場向けのセミナーも開催しています。
ホームページにセミナーの専用ページを開設しておりますので、産業保健活動の取組みにお役立てください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/seminar
※以下のセミナーは全て日医認定産業医の単位取得はできません。産業医の皆様におかれましては、予めご了承ください
*★=================================★*
働く女性の健康セミナーのご案内【新規ご案内】
*★=================================★*
女性活躍推進法が施行され、企業における女性の活躍推進が求められている今、女性の健康支援をすることは、企業にとって、長期的な人材の確保や生産性の向上といったメリットをもたらすとともに、人材の定着に基づくキャリアアップや管理職登用につながることも期待されます。少子高齢化により人材不足が深まる中、増々期待される女性の活躍を推進するうえで、女性の健康支援は、欠かせない取り組みです。
女性が働きやすい職場は、男女ともに働きやすい職場につながります。
女性の健康支援を通じて、誰もが健康で生き生きと働くことのできる職場づくりに、取り組んでいただく機会として、今回セミナーを開催します。
是非、ご参加ください。
※今回のセミナーは日医認定産業医の単位取得はできません。
産業医の皆様におかれましては、予めご了承ください。
| 日 時 | 令和7年1月26日(日)14時00分~16時00分 |
|---|---|
| 会 場 | 鹿児島市立天文館図書館 4階交流スペース (鹿児島市千日町1-1 センテラス天文館) |
| 対象者 | どなたでも(参加無料) |
| 内 容 |
|
| 定 員 | 40名 |
| 申 込 方 法 |
メールフォーム https://ssl.formman.com/t/rtbm/ ※令和7年1月20日(月)までにお申し込みください。 |
※このセミナーでは、「働く女性のキャリア個別相談会(事前予約制)」も開催します。時間は、13時から14時までで、場所はセミナーと同じ会場です。
お知らせ
<鹿児島産業保健総合支援センター>
産業保健に関するご質問・ご相談を受け付けています。
治療と仕事の両立支援対策やメンタルヘルス対策をはじめ、産業保健に関する様々なご質問・ご相談を受け付けています。(オンラインによる相談も可能です。)電話やFAX、ホームページからお気軽にご相談ください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/otoiawase
▼「さんぽセンターWebひろば」の専用ページ
https://www.johas.go.jp/Portals/0/sanpocenter/webhiroba.html
治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立に関するお悩み等について、事業場関係者や産業保健スタッフ、がんなど反復・継続して治療が必要な患者(労働者)やその家族からの相談に、当センターのメンタルヘルス対策・両立支援促進員又は産業保健専門職(保健師)が相談に応じます。(オンラインによる相談も可能です。)
両立支援に関する相談、各種支援は無料です。
▼治療と仕事の両立支援(支援内容、相談窓口、申込フォームなど)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/cat765
医療機関の両立支援(出張)相談窓口につきましては、事前予約の状況等により、窓口業務を中止する可能性がありますので、当センターのホームページで事前に確認いただきますようお願いいたします。
▼「治療と仕事の両立支援(出張)相談窓口」を新たに開設しました
当センターでは、「社会医療法人博愛会相良病院」と令和6年11月13日に治療と仕事の両立支援事業実施に係る協定を締結し、同年12月10日より「両立支援(出張)相談窓口」を開設します。開設の日時は、次のとおりとなっています。
○相良病院(開設日:令和6年12月10日(火))
日時:毎月 第2火曜日 10:00~12:00(ただし、祝日は除く)
場所:相良病院 がん相談支援センター(TEL 099-216-3360)
※事前予約制となります。
※予約につきましては、月から金曜の9:00~17:30となります。
詳細については、こちらをご確認ください。
○相良病院 両立支援相談窓口案内チラシ
https://kagoshimas.johas.go.jp/wp-content/uploads/2024/11/R6.11_sagara.pdf
▼「治療と仕事の両立支援」の専用ページ
https://www.ryoritsushien.johas.go.jp/blackjack/
メンタルヘルス対策支援について
当センターのメンタルヘルス対策・両立支援促進員(産業カウンセラーや社会保険労務士など)が事業場に訪問し、職場のメンタルヘルス対策に関する取り組みを無料で支援します。
また、事業場訪問以外のご相談(対面・電話・メール・オンライン)にも対応いたします。オンラインによる研修も対応可能です。
▼メンタルへルス対策支援(支援内容、申込フォームなど)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/mental
運動指導等支援について
健康で安心して働ける職場環境の形成を支援するという産業保健の観点から、運動指導等を通じた労働者の健康保持増進について取り組むため、産業保健相談員(健康運動指導士)による個別訪問支援等を実施しています。事業場が行う健康教育等において、是非、ご活用ください。
▼運動指導等支援(支援内容、申込フォーム)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/undou
地域産業保健センター(地域窓口)について
各地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業主や労働者を対象に、健康診断結果の意見聴取、健康相談、長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導、保健指導等の産業保健サービスを無料で行っています。
▼地域産業保健センターについて
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/cat638
<労働者健康安全機構情報>
労災疾病等医学研究普及サイトのご案内
労働者健康安全機構では、労働災害の発生状況や行政のニーズを踏まえ、労災補償政策上重要なテーマや新たな政策課題について、時宜に応じた研究に取り組んでいます。
▼労災疾病等医学研究普及サイト
https://www.research.johas.go.jp/index.html
▼「生活習慣病」について
https://www.research.johas.go.jp/seikatsu2018/index.html
▼「メンタルヘルス」について
https://www.research.johas.go.jp/mental2018/index.html
▼「アスベスト」について
https://www.research.johas.go.jp/asbesto2018/
▼「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」について
★両立支援コーディネーターマニュアルはこちら
https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1047/Default.aspx
★両立支援コーディネーターについて知りたい方はこちら
https://www.research.johas.go.jp/ryoritsucoo/
▼「病職歴データベースを活用した研究」について
https://www.research.johas.go.jp/bs/
<厚生労働省情報>
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
転倒予防・腰痛予防の取組について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html
<鹿児島労働局情報>
鹿児島県内の労働災害発生状況
◯令和6年発生分(10月末)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html
最新の業種別労働災害発生状況
⇒「令和6年における業種別労働災害発生状況」をクリック
<情報提供>
令和6年度難病患者就労支援セミナーのご案内
【鹿児島県難病相談・支援センター】
医療の進歩により多くの難病の慢性疾患化が進み、疾患の治療を続けながら職業生活を含む普通の日常生活を送ることができる難病患者が増えています。その一方で、難病のある人たちの多くが、就職や仕事を継続する際に、治療と仕事の両立等で困難に直面している現状があります。
本セミナーは支援者や企業等が難病および難病患者の就労についての理解を深め、難病患者へのより良い就労支援が行えるように開催するものです。
主催は鹿児島県難病相談・支援センターとなります。是非、ご参加ください。
| 【日 時】 | 令和7年1月24日(金)13時00分から16時00分 (受付12時30分~) |
|---|---|
| 【場 所】 | ハートピアかごしま 2階 大会議室(鹿児島市小野1丁目1-1) |
| 【対 象】 | 難病患者の雇用に関心のある企業、福祉サービス事業所 難病患者支援を行う医療機関、障害者就業・生活支援センター 行政職員(難病担当者等) 等 |
| 【定 員】 | 50名程度 |
【お問合せ先】
鹿児島県難病相談・支援センター 相談課(ハートピアかごしま 3階)
電話 099-218-3133(但し、火曜・祝日を除く 9:00~16:00)
≪当センターホームページでのお知らせ≫
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/070124_syuroshienseminar
所長コラム
令和6年も終わろうとしている。「治療と仕事の両立支援」が始まって6年、「働き方改革」は9年経過。両施策の効果はどれほど得られたであろうか。これらは雇用する従業員の労働時間の在り様が中心的な施策。働く人にとっては望ましいこと。その一方で、働き手不足の中で最賃の大幅アップも行なわれ、特に地方の小規模・零細規模の事業場の経営状況は一段と厳しさを増しているようだ。
長時間労働対策の中心として残業時間制限が注目されるが、作業自体の効率化ができなければ働き手の増員で対応することになる。が、それは人件費の高騰を意味し経営に苦慮する事業場にとっては死活問題。そもそも働き手不足の状況では労働力確保すら難題。既に3K労働等は外国人労働者に頼る状況が常態化している。下請け・孫請け事業場においては「働き方改革」や「両立支援」に取り組む余裕などないのが実態のようだ。
上記の両施策実践のためには経営努力だけで無く事業場の作業効率向上が必須。効率化の中心は作業の機械化や自動化よりも無駄な作業の排除である。自然を相手とする生産業等では限界があるが、事務作業だけでなく製造業等でもIT活用等での効率化は望めるが、それ以上に重要なのは無駄な作業を排除すること。そのためには前例踏襲ではなく常に業務分析を行なって効率化を図ること。価値生産に資する業務を中心に、業務分析・改善こそが最重要と思われる。
政治・経済状況の流動化が増し来年にはさらに混迷を深めそうであるが、そういう時こそ、日々の作業の業務分析は不可欠であろう。