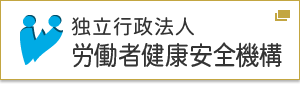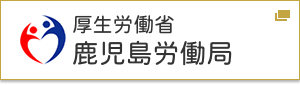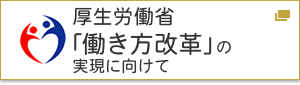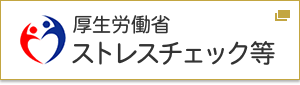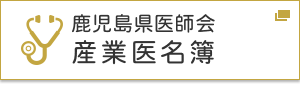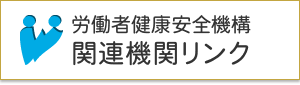メールレター 第270号
■■■sanpo■■■■■■■■■■■■■■■■■■
≪「さんぽ鹿児島」メールレター≫ 第270号(2025.9)
発行:鹿児島産業保健総合支援センター
所長 草野 健
■■■■■■■■■■■■■■■■kagoshima■■■
相談員からのメッセージ
ストレスチェックの成果は本当にあるの?
産業保健相談員 桶谷 薫
(鹿児島県民総合保健センター)
(担当分野:産業医学)
ストレスチェックって本当に成果は上がっているのでしょうか?
というお声をよく耳にします。
そこで 厚労省調査研究結果の一部をまとめてみました。
【労働者のメンタルヘルスの意識向上】
ストレスチェック制度開始により50.2%の労働者が自身のストレスを意識することとなったと回答。
【労働生産性の向上】
ストレスチェックを実施し、職場環境改善の取り組みをした労働者はストレスチェック未実施の労働者と比較して労働生産性が向上したと回答率が有意に高い。
【事業場のメンタルヘルス対策の促進】
ストレスチェックを開始していない事業場と比較して、開始した事業場は30%以上多くメンタルヘルス対策が拡充されていっている。メンタルヘルスに理解ある風土が広がることで以前と比較しメンタルヘルス不調者が5分の1に低下した。
【1か月以上の疾病休業の実態調査】
高ストレス者は1年間の追跡の結果、疾病1か月以上の休業のハザード比は高ストレス者以外と比較して男性6.6倍、女性2.8倍であった。
【離職者の実態調査】
高ストレス者は3年間の追跡調査の結果、高ストレス者以外と比較してハザード比で男性2.86倍、女性1.52倍であった。
労働者の気づきを促すとともに、ストレスチェックの結果をもとに事業所が職場環境改善につなげ働きやすい職場作りを実施していくことが大切な労働者のメンタル不調の未然防止につなげることができるという調査研究結果が他にも多くあがっています。
数年以内には50人以上の事業所だけではなく全事業所でストレスチェックがいよいよはじまります。多くの労働者に受けていただけますように厚労省調査研究結果をぜひ参考にされてみてください。
産業保健研修会のご案内(9~11月開催分 受付中!)
┏―[ 産業保健研修会の詳細・申込はこちらから ]―――――┓
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h2335
┗――――――――――――――――――――――――――――┛
産業保健研修会の申込方法の変更に関する重要なお知らせです!
お申込み時の個人情報の管理を徹底するため、令和7年4月からFAXでのお申込みを廃止しております。
お申込みフォームもしくはホームページからの手続きとなります。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
日医認定産業医(生涯研修も対象)の皆様へ重要なお知らせです。
当センターが実施する研修においてもMAMISのマイページ登録完了が必要です。
詳細は鹿児島県医師会ホームページをご覧ください。
https://www.kagoshima.med.or.jp/doctors/news/4630/
当センター主催のセミナーのご案内
当センターでは産業保健研修会以外に、事業場向けのセミナーも開催しています。
ホームページにセミナーの専用ページを開設しておりますので、産業保健活動の取組みにお役立てください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/seminar
*★=================================★*
≪新規≫おとなの発達障がいセミナー【オンライン・参加無料】
*★=================================★*
発達障がいの特性の理解を深めていただき、その特性による職場での問題点を「事例性」としてとらえ、本人が働く上で感じる「困りごと」を含めた、職場の「困りごと」に焦点を当てたマネジメントをご紹介します。
| 日時 | 令和7年12月5日(金)13時30分から16時30分 |
| 演題 | メンタルヘルスと発達障がい特性の理解について |
| 講師 | 井上 幸紀 先生 大阪産業保健総合支援センター産業保健相談員 大阪公立大学大学院医学研究科 神経精神医学 教授 |
| 演題 | 発達特性を有する労働者の職場での事例性に応じた対応と専門家との連携について |
| 講師 | 永田 昌子 先生 福岡産業保健総合支援センター産業保健相談員 産業医科大学 医学部 両立支援室 室長 |
参加者には、セミナー資料として使用します「おとなの発達障がいマネジメントハンドブック」を事前に郵送いたします(無料)
▼【オンライン】おとなの発達障がいセミナー申込みフォーム
https://ssl.formman.com/t/eIQA/
申込締切 令和7年11月17日(月)まで(先着順となります)
▼詳しくはホームページをご覧ください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/071205_webseminar
※日医認定産業医の単位取得はできません。産業医の皆様におかれましては、予めご了承ください。
*★=================================★*
≪再掲≫産業医による産業保健研修会のご案内[土曜日開催]
*★=================================★*
講師:
鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員(産業医学)
冨宿 明子 先生
紹介:
県内の事業場の産業医として約20年間に渡りご活動されており、労働衛生コンサルタント(保健衛生)としてもご活躍されています。
| 開 催 日 時 |
|
|---|
【会場】全て鹿児島県医師会館(鹿児島市中央町8-1)
※詳しくはホームページをご覧ください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/seminar#R7.sat.seminar
▼産業医による産業保健研修会(土曜日開催)申込フォーム(各開催日の前日の午前中まで)
https://ssl.formman.com/t/rtbm/
※こちらからのお申込みによる日医認定産業医の単位取得はできません。
産業医の皆様におかれましては、予めご了承ください。
お知らせ
<鹿児島産業保健総合支援センター>
産業保健に関するご質問・ご相談を受け付けています。
治療と仕事の両立支援やメンタルヘルス対策をはじめ、産業保健に関する様々なご質問・ご相談を受け付けています。(オンラインによる相談も可能です。)電話やホームページからお気軽にご相談ください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/otoiawase
▼「さんぽセンターWebひろば」の専用ページ
https://www.johas.go.jp/Portals/0/sanpocenter/webhiroba.html
治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立に関するお悩み等について、事業場関係者や産業保健スタッフ、がんなど反復・継続して治療が必要な患者(労働者)やその家族からの相談に、当センターのメンタルヘルス対策・両立支援促進員又は産業保健専門職(保健師)が相談に応じます。(オンラインによる相談も可能です。)
両立支援に関する相談、各種支援は無料です。
▼治療と仕事の両立支援(支援内容、相談窓口、申込フォームなど)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/cat765
医療機関の両立支援(出張)相談窓口につきましては、事前予約の状況等により、窓口業務を中止する可能性がありますので、当センターのホームページで事前に確認いただきますようお願いいたします。
▼「治療と仕事の両立支援」の専用ページ
https://www.ryoritsushien.johas.go.jp/blackjack/
メンタルヘルス対策支援について
当センターのメンタルヘルス対策・両立支援促進員(産業カウンセラーや社会保険労務士など)が事業場に訪問し、職場のメンタルヘルス対策に関する取り組みを無料で支援します。
また、事業場訪問以外のご相談(対面・電話・メール・オンライン)にも対応いたします。オンラインによる研修も対応可能です。
▼メンタルへルス対策支援(支援内容、申込フォームなど)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/mental
運動指導等支援について
健康で安心して働ける職場環境の形成を支援するという産業保健の観点から、運動指導等を通じた労働者の健康保持増進について取り組むため、産業保健相談員(健康運動指導士、理学療法士)による個別訪問支援等を実施しています。事業場が行う健康教育等において、是非、ご活用ください。
▼運動指導等支援(支援内容、申込フォーム)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/undou
地域産業保健センター(地域窓口)について
各地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業主や労働者を対象に、健康診断結果の意見聴取、健康相談、長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導、保健指導等の産業保健サービスを無料で行っています。
▼地域産業保健センターについて
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/cat638
<労働者健康安全機構情報>
労災疾病等医学研究普及サイトのご案内
労災疾病等医学研究普及サイトは、これまでの労災疾病等医学研究成果のほか、両立支援事業、予防医療事業等について掲載し、事業を広く周知する専用のサイトとして運用してきたところです。今般、当サイトの情報を労働者健康安全機構ホームページ内へ移設・統合することとなりました。
変更後リンク先
https://www.johas.go.jp/kenkyu_kaihatsu/rosaisippei13bunya/tabid/398/Default.aspx
★「脊柱靭帯骨化症」
★「高年齢労働者の転倒災害」
★「妊娠時の食・生活習慣」
★「高血圧性心疾患」
★「脂肪性膵疾患」
★「じん肺」
★「アスベスト」
「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」について
▼両立支援コーディネーターマニュアルはこちら
https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1047/Default.aspx
▼「両立支援コーディネーター基礎研修」について
https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/2126/Default.aspx
「病職歴データベースを活用した研究」について
https://www.research.johas.go.jp/bs/
「石綿関連疾患診断技術研修(基礎・読影研修)」について
石綿(アスベスト)は、かつて建設資材や自動車部品などに利用されてきましたが、石綿繊維を吸入すると肺がんや中皮腫など石綿関連疾患発症の原因となるため、現在は製造・使用等が禁止されています。
石綿関連疾患の診断及び石綿ばく露所見の判定にはエックス線写真の読影等が必要となりますが、その判断が難しい事例が多く、医学的な知識・経験に加え、石綿ばく露等についての知識も必要となります。
当機構では、呼吸器系の疾患を取り扱う医師や産業医などの医療関係者を対象に、石綿関連疾患の診断技術の向上及び労災補償制度の周知を図るため、最新の医学的知見や診断技術を踏まえた石綿関連疾患の診断方法、石綿ばく露の所見に関する読影方法及び労災補償制度の取扱い等についての研修を実施しています。
今年度の研修日程・内容は、「労災疾病等医学研究普及サイト」
https://www.research.johas.go.jp/asbestokenshu/
に掲載していますのでご覧ください(本研修は日本医師会認定産業医の単位取得対象です)。
また、申込み方法のお問い合わせは、参加を希望される開催地に所在する産業保健総合支援センターまでお願いいたします。
【産業保健総合支援センター一覧】
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx
「第18回じん肺診断技術研修」について
当機構では、じん肺健康診断に従事する医師が必要な法制度の知識及び専門技術を修得することを目的とした研修会を毎年1回開催しています。
この研修は、長年臨床や医学研究に従事したじん肺専門医師が講師を務め、テキストは講師を務める医師が研究で得られた治療方法、労災補償上で重要となる診断法等の解説、最新知見をまとめた冊子を使用しており、内容が分かりやすいと大変好評を得ています。
https://www.research.johas.go.jp/jinpai2015/index.html
なお、本研修を全て受講しますと、日本医師会認定産業医制度に係る認定単位9.5単位(生涯研修単位のみ)、日本職業・災害医学会が認定する労災補償指導医制度の認定単位2単位(選択単位 業務上疾病の労災補償)が取得できます。(単位申請中)
https://www.research.johas.go.jp/jinpaikenshu/
<厚生労働省情報>
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
転倒予防・腰痛予防の取組について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html
令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について(再掲)
https://www.mhlw.go.jp/stf/coolwork_20250228.html
<鹿児島労働局情報>
職場における熱中症対策の強化について
~令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます~
職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されます。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
「職場の健康診断実施強化月間」の実施について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施について、改めて徹底するため、平成 25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的な指導を行っています。
令和7年度全国労働衛生週間(第76回)について
「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、「労働衛生」に関する国民の意識を高め、事業場における自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的として、毎年実施しています。
令和7年度全国労働衛生週間は、
『ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場』
をスローガンとし、10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間として全国的に展開されます。
鹿児島県内の労働災害発生状況
◯令和7年発生分(7月末)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html
最新の業種別労働災害発生状況
⇒「令和7年における業種別労働災害発生状況」をクリック
所長コラム
「温故知新」ということが政治経済社会現象だけでなく自然現象にも無力のようにも思われる時代である。経済動向を予測するには常にある程度の前提が必要だがその前提は自然現象も大きく影響し日々変化している。労働とは付加価値を産み出す営為であり、付加価値とは直接間接の使用価値であるべきと思う。最も基本的な価値生産業は食料生産業であることには異論はないと思うが、現実の経済活動は株価や為替動向に大きく影響され交換価値中心に動いているように感じる。
労働衛生・産業保健活動の対象は「働く人」で、その中心は事業場に雇用され賃金を得て労働を提供する者。この定義からは雇用主や自営業者、また児童生徒学生に一部の療養者や高齢年金生活者は対象から除外される。然しながら、実際の労働現場ではアルバイトに勤労奉仕者など多様な人が働く。加えて最近では外国人の技能実習生も増加する傾向にある。
産業医学は社会医学そのものであり、自然科学としての医学を大前提としながら社会科学・人文科学も幅広く応用する必要がある。産業医だけでなく産業保健活動に携わる者は近視眼的に眼前の現場・「労働」している人のみでなく広範に社会の中で生活する全ての人を対象とし、社会の在り様に眼を向け広い視野を持つことが必須である。
「本当に良い医者とは幅広く深い教養を持つ医者」という恩師の言葉を度々思い出している。