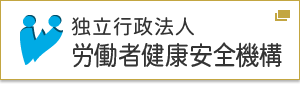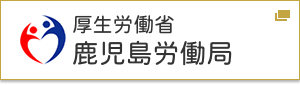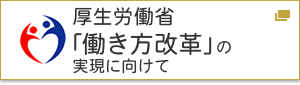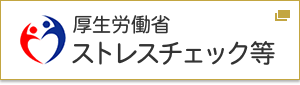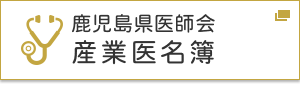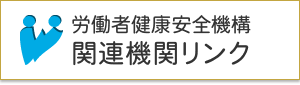メールレター 第272号
■■■sanpo■■■■■■■■■■■■■■■■■■
≪「さんぽ鹿児島」メールレター≫ 第272号(2025.11)
発行:鹿児島産業保健総合支援センター
所長 草野 健
■■■■■■■■■■■■■■■■kagoshima■■■
相談員からのメッセージ
結核対策と保健所
産業保健相談員 徳留 修身
(担当分野:結核対策、喫煙対策、産業保健)
わが国の保健所は戦前から設置が始まり、富国強兵の時代において結核と乳児死亡への対策は最重要課題であった。保健所は早くからX線撮影装置を設置し、また結核治療を行った時期もある。単独の「結核予防法」が制定され、予防、診断、治療、集団感染対策、再発防止などについて多くの基準やそれに伴う指針、ガイドライン等も作成されてきた。公費の支出には基準に従うことが条件となる。結核予防法は現在「感染症法」に組み込まれている。しかし罹患率の低下に伴い「結核対策」を系統的に学習する機会は減少しているように思われる。対策の検討には集団を対象とする公衆衛生の視点が欠かせない。
事業所(集団)内で結核患者が発生した場合に、「その患者を診断した医師は保健所に患者発生届を提出したか」、「感染経路の推定は可能か」、「接触者の範囲をどこまでとするか」、「検査対象、検査項目と実施時期」など、「結核対策」として検討すべき課題は多い。事業所はこれらについて保健所からの提案や指示に従う必要があり、産業医は事業所職員の健康情報の把握や職員への健康教育・相談のほかに、事業所と保健所との相互協力を支援する役割もある。事業所が保健所からの調査や指示を受ける前に、急いで独自の対策を進めたために混乱が生じた例もある。保健所は結核対策の第一線機関としての歴史を有している。保健所職員(医師、保健師、放射線技師等)は日ごろから多くの結核事例を経験しているうえ、研修の機会も提供されている。研修は結核予防会結核研究所(東京都清瀬市)が担当しており概要はホームページに掲載されている。同研究所は国際研修も実施しており、結核の研修を英語で行う世界で唯一の機関とされる。高蔓延国の結核を減らすことはわが国の結核状況をさらに改善させることにもつながる。2024年にわが国で発生した結核患者に占める「外国生まれ」の割合は10代で約80%、20代で90%、30代で約70%となっており、「日本生まれ」を大きく上回っている。結核が流行している国で感染し、来日して発病するというパターンである。発病者の出身国は多い順にインドネシア、フィリピン、ネパール、ミャンマー、ベトナムであった(2024年)。技能実習生など外国人労働者や留学生を抱える事業所や学校では、咳や痰などの症状が2週間以上続くなら結核の可能性も考慮し、早期発見や集団感染の防止に努める必要がある。
産業保健研修会のご案内(11~1月開催分 受付中!)
┏―[ 産業保健研修会の詳細・申込はこちらから ]―――――┓
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h2335
┗――――――――――――――――――――――――――――┛
産業保健研修会の申込方法の変更に関する重要なお知らせです!
お申込み時の個人情報の管理を徹底するため、令和7年4月からFAXでのお申込みを廃止しております。
お申込みフォームもしくはホームページからの手続きとなります。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
日医認定産業医(生涯研修も対象)の皆様へ重要なお知らせです。
当センターが実施する研修においてもMAMISのマイページ登録完了が必要です。
詳細は鹿児島県医師会ホームページをご覧ください。
https://www.kagoshima.med.or.jp/doctors/news/4630/
認定医研修会単位につきましては、日本医師会に登録申請を行っており、MAMISマイページへの受講実績の反映は目安として開催日から1か月程度を想定しております。
ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
当センター主催のセミナーのご案内
当センターでは産業保健研修会以外に、事業場向けのセミナーも開催しています。
ホームページにセミナーの専用ページを開設しておりますので、産業保健活動の取組みにお役立てください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/seminar
*★=================================★*
≪再掲≫産業医による産業保健研修会のご案内[土曜日開催]
*★=================================★*
講師:
鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員(産業医学)
冨宿 明子 先生
紹介:
県内の事業場の産業医として約20年間に渡りご活動されており、労働衛生コンサルタント(保健衛生)としてもご活躍されています。
| 開 催 日 時 |
|
|---|
【会場】全て鹿児島県医師会館(鹿児島市中央町8-1)
※詳しくはホームページをご覧ください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/seminar#R7.sat.seminar
▼産業医による産業保健研修会(土曜日開催)申込フォーム(各開催日の前日の午前中まで)
https://ssl.formman.com/t/rtbm/
※こちらからのお申込みによる日医認定産業医の単位取得はできません。
産業医の皆様におかれましては、予めご了承ください。
お知らせ
<鹿児島産業保健総合支援センター>
産業保健に関するご質問・ご相談を受け付けています。
治療と仕事の両立支援やメンタルヘルス対策をはじめ、産業保健に関する様々なご質問・ご相談を受け付けています。(オンラインによる相談も可能です。)電話やホームページからお気軽にご相談ください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/otoiawase
▼「さんぽセンターWebひろば」の専用ページ
https://www.johas.go.jp/Portals/0/sanpocenter/webhiroba.html
治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立に関するお悩み等について、事業場関係者や産業保健スタッフ、がんなど反復・継続して治療が必要な患者(労働者)やその家族からの相談に、当センターのメンタルヘルス対策・両立支援促進員又は産業保健専門職(保健師)が相談に応じます。(オンラインによる相談も可能です。)
両立支援に関する相談、各種支援は無料です。
▼治療と仕事の両立支援(支援内容、相談窓口、申込フォームなど)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/cat765
医療機関の両立支援(出張)相談窓口につきましては、事前予約の状況等により、窓口業務を中止する可能性がありますので、当センターのホームページで事前に確認いただきますようお願いいたします。
▼「治療と仕事の両立支援」の専用ページ
https://www.ryoritsushien.johas.go.jp/blackjack/
メンタルヘルス対策支援について
当センターのメンタルヘルス対策・両立支援促進員(産業カウンセラーや社会保険労務士など)が事業場に訪問し、職場のメンタルヘルス対策に関する取り組みを無料で支援します。
また、事業場訪問以外のご相談(対面・電話・メール・オンライン)にも対応いたします。オンラインによる研修も対応可能です。
▼メンタルへルス対策支援(支援内容、申込フォームなど)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/mental
運動指導等支援について
健康で安心して働ける職場環境の形成を支援するという産業保健の観点から、運動指導等を通じた労働者の健康保持増進について取り組むため、産業保健相談員(健康運動指導士、理学療法士)による個別訪問支援等を実施しています。事業場が行う健康教育等において、是非、ご活用ください。
▼運動指導等支援(支援内容、申込フォーム)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/undou
地域産業保健センター(地域窓口)について
各地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業主や労働者を対象に、健康診断結果の意見聴取、健康相談、長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導、保健指導等の産業保健サービスを無料で行っています。
▼地域産業保健センターについて
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/cat638
<労働者健康安全機構情報>
労災疾病等医学研究普及サイトのご案内
労働者健康安全機構では、労働災害の発生状況や行政のニーズを踏まえ、労災補償政策上重要なテーマや新たな政策課題について、時宜に応じた研究に取り組んでいます。
▼労災疾病等医学研究・開発ページ
労災疾病等医学研究普及サイトは、これまでの労災疾病等医学研究成果のほか、両立支援事業、予防医療事業等について掲載し、事業を広く周知する専用のサイトとして運用してきたところです。今般、当サイトの情報を労働者健康安全機構ホームページ内へ移設・統合することとなりました。
変更後リンク先
https://www.johas.go.jp/kenkyu_kaihatsu/rosaisippei13bunya/tabid/398/Default.aspx
★「脊柱靭帯骨化症」
★「高年齢労働者の転倒災害」
★「妊娠時の食・生活習慣」
★「高血圧性心疾患」
近年、心不全患者が急増していますが、その原因は多岐にわたります。高血圧が原因の心不全では、心収縮能は保たれているにもかかわらず拡張機能が低下する例と、極端に心機能が低下する例が認められています。
令和6年度から開始した研究「左室駆出率が低下した心不全を呈する高血圧性心疾患に関連するバイオマーカーの同定と早期診断・治療戦略の開発」では、心不全を発症した高血圧患者において、特定の遺伝子が心機能低下に関与するかを検討しています。
将来的に心機能の低下が予測される高血圧患者を同定することで重症心不全発症予防に寄与できる可能性があります。
本研究により、現時点では明らかでない高血圧の心筋線維化に及ぼす分子メカニズムが解明できれば、発症予測アルゴリズムの構築、新薬の開発など、さまざまな臨床応用に道を開くことができます。高血圧を指摘される勤労年代において遺伝子レベルでの解析が進むことで、より早期からの治療介入が可能となり将来的に心機能が低下して発症する心不全のリスクを低減することが期待されます。
▼本研究詳細については以下URLからご覧ください。
https://www.johas.go.jp/kenkyu/rosaisippei13bunya/tabid/2538/Default.aspx
★「脂肪性膵疾患」
★「じん肺」
★「アスベスト」
「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」について
▼両立支援コーディネーターマニュアルはこちら
https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1047/Default.aspx
▼「両立支援コーディネーター基礎研修」について
https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/2126/Default.aspx
<厚生労働省情報>
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
転倒予防・腰痛予防の取組について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html
<鹿児島労働局情報>
鹿児島県内の労働災害発生状況
◯令和7年発生分(9月末)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html
最新の業種別労働災害発生状況
⇒「令和7年における業種別労働災害発生状況」をクリック
<その他>
令和7年度若年性認知症セミナー【鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課】
| 日 時 | 令和7年12月16日(火) 13:00~16:00(12:30 より受付開始) |
|---|---|
| 会 場 | 県庁2階 講堂(鹿児島市鴨池新町10番1号)※集合形式 |
| 詳 細 | https://kagoshimas.johas.go.jp/information/071216_seminar |
| 申 込 期 限 |
令和7年12月2日(火) |
| 申 込 方 法 |
URLより電子申請にてお申込みください。 https://shinsei.pref.kagoshima.jp/G5kedLuR |
| お問合せ先 | 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課 認知症・生活支援係 電話 099-286-2698 |
所長コラム
漸く「夏日」が終わったが、爽やかな秋は長い夏から短い冬への短い移行期間に過ぎないような予感。気候変動は地球環境の微変動に過ぎず人為的影響は小さい、との言説もあるがいずれにしても自然環境の変化は人間社会の在り様にも影響を与える。そうしたなか我が国初の女性首相が誕生した。ジェンダーの問題からは好ましい変化で内閣の顔ぶれも一新した。高市政権がどのような政策を行なうか注視したい。
少数与党でありしかも世界的に政治動向が不安定下での政権運営には厳しいものがあると思われる。日本の経済成長を第一に掲げているが、物的資源に乏しく生産人口も減少し続けている状況では個々の労働生産性を挙げることが必須になる。その意味で「馬車馬のように働く」とか「ライフワークバランスという言葉を捨てる」とかの言葉は首相自身や国会議員と高級官僚だけに限定されたもの、と捉えたいが早速に経済界からは歓迎の言葉も聞こえてくる。さらに労働時間規制の緩和を、との声も出ている。
極めて不十分ながらも「働き方改革」の諸施策が漸く浸透し始めた状況に逆行するのではとの危惧も抱く。長時間労働規制推進に対する今以上の予算措置は少なくとも期待できそうにない。であれば、肝心なのは生産性を阻害する作業をなくす対策こそが重要となる。株価は上昇しているもののインフレ進行で中小零細企業の経営は厳しさを増している。健康経営という思想の下、「寝食を忘れて働く」のではなく「寝食も大事にしながら生産性を挙げる」ために智慧を絞ることが必須となる。「金がなければ智慧を出せ」という言葉が重くなる時代になりそうだ。