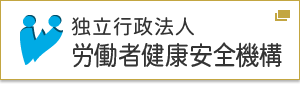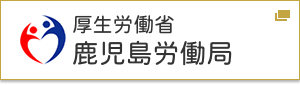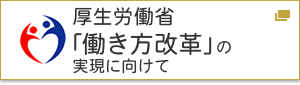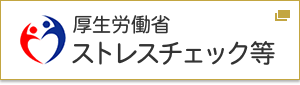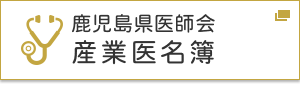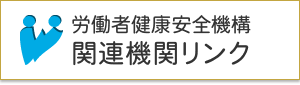メールレター 第268号
■■■sanpo■■■■■■■■■■■■■■■■■■
≪「さんぽ鹿児島」メールレター≫ 第268号(2025.7)
発行:鹿児島産業保健総合支援センター
所長 草野 健
■■■■■■■■■■■■■■■■kagoshima■■■
相談員からのメッセージ
【実食レポ】アイススラリーを食べてみた
産業保健相談員 冨宿 明子
(担当分野:産業医学)
今シーズン、熱中症予防関係の記事をいろいろと読んでいると、「アイススラリー(ICE SLURRY)」という見慣れない字面をよく見かけます。
調べてみると、アイススラリーとは、液体に微小な氷粒子と液体が混ざり合った流動性のあるシャーベット状態のこと、だとか。
そこで早速、最もメジャーなスポーツドリンクが商品名の頭に付いたアイススラリーを通販で取り寄せて、風呂あがりに実食してみました!
持った感じは「小さな●ーリッシュ」という感じなのですが、とけたら食べられたもんじゃないクー●ッシュとは違って、常温で取り寄せて、家の冷凍庫で凍らせながら保管できます。
凍ってカチカチの状態のパウチを女性の力で20秒ほど揉むと、ふっと柔らかくなります。
揉むという過程でも、手のひらの血管から体が冷えていく感じがします。
さて実食。
もにゅっとしたシャーベットの食感で、ごくんと美味しく飲み込めました。
そして風呂あがりにもかかわらず、ファンデーションを顔に塗ることができるくらいすぐに汗がひきました!
欠点は、1パウチ300円というお値段と、まだ手軽に近所で買えないことですね。
これから普及して、手軽に買うことができるようになるのを期待します。
以上、アイススラリーの実食レポでした。
産業保健研修会のご案内(7~9月開催分 受付中!)
┏―[ 産業保健研修会の詳細・申込はこちらから ]―――――┓
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h2335
┗――――――――――――――――――――――――――――┛
産業保健研修会の申込方法の変更に関する重要なお知らせです!
お申込み時の個人情報の管理を徹底するため、令和7年4月からFAXでのお申込みを廃止しております。
お申込みフォームもしくはホームページからの手続きとなります。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
日医認定産業医(生涯研修も対象)の皆様へ重要なお知らせです。
当センターが実施する研修においてもMAMISのマイページ登録完了が必要です。
詳細は鹿児島県医師会ホームページをご覧ください。
https://www.kagoshima.med.or.jp/doctors/news/4630/
当センター主催のセミナーのご案内
当センターでは産業保健研修会以外に、事業場向けのセミナーも開催しています。
ホームページにセミナーの専用ページを開設しておりますので、産業保健活動の取組みにお役立てください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/seminar
*★=================================★*
≪再掲≫産業医による産業保健研修会のご案内[土曜日開催]
*★=================================★*
講師:
鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員(産業医学)
冨宿 明子 先生
紹介:
県内の事業場の産業医として約20年間に渡りご活動されており、労働衛生コンサルタント(保健衛生)としてもご活躍されています。
| 開 催 日 時 |
|
|---|
【会場】全て鹿児島県医師会館(鹿児島市中央町8-1)
※詳しくはホームページをご覧ください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/seminar#R7.sat.seminar
▼産業医による産業保健研修会(土曜日開催)申込フォーム(各開催日の前日の午前中まで)
https://ssl.formman.com/t/rtbm/
※こちらからのお申込みによる日医認定産業医の単位取得はできません。
産業医の皆様におかれましては、予めご了承ください。
*★=================================★*
≪再掲≫対象となる事業場の皆様!
化学物質の自律的な管理の取り組みは進んでいますか?
*★=================================★*
| 日 時 | 令和7年7月17日(木)18:00~20:00 |
|---|---|
| 会 場 | 光健ボイスビル 2階(鹿児島市上之園町25-36) |
| テーマ | 自律的な化学物質管理とリスクアセスメント |
| 講 師 | 産業保健相談員 中甫木 直樹 先生(労働衛生工学) |
| 定 員 | 10名(先着順となります) |
| 日 時 | 令和7年8月30日(土)14:00~16:00 |
|---|---|
| 会 場 | 鹿児島県医師会館 3階 中ホール(鹿児島市中央町8-1) |
| テーマ | 化学物質のリスクアセスメント (クリエイトシンプルを用いたリスクの見積り手法) |
| 講 師 | 産業保健相談員 田原 崇志 先生(労働衛生工学) |
| 定 員 | 30名(先着順となります) |
▼化学物質セミナー申込フォーム(各開催日の前日の午前中まで)
https://ssl.formman.com/t/gFqY/
※こちらからのお申込みによる日医認定産業医の単位取得はできません。
産業医の皆様におかれましては、予めご了承ください。
お知らせ
<鹿児島産業保健総合支援センター>
産業保健に関するご質問・ご相談を受け付けています。
治療と仕事の両立支援やメンタルヘルス対策をはじめ、産業保健に関する様々なご質問・ご相談を受け付けています。(オンラインによる相談も可能です。)電話やホームページからお気軽にご相談ください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/otoiawase
▼「さんぽセンターWebひろば」の専用ページ
https://www.johas.go.jp/Portals/0/sanpocenter/webhiroba.html
治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立に関するお悩み等について、事業場関係者や産業保健スタッフ、がんなど反復・継続して治療が必要な患者(労働者)やその家族からの相談に、当センターのメンタルヘルス対策・両立支援促進員又は産業保健専門職(保健師)が相談に応じます。(オンラインによる相談も可能です。)
両立支援に関する相談、各種支援は無料です。
▼治療と仕事の両立支援(支援内容、相談窓口、申込フォームなど)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/cat765
医療機関の両立支援(出張)相談窓口につきましては、事前予約の状況等により、窓口業務を中止する可能性がありますので、当センターのホームページで事前に確認いただきますようお願いいたします。
▼「治療と仕事の両立支援」の専用ページ
https://www.ryoritsushien.johas.go.jp/blackjack/
メンタルヘルス対策支援について
当センターのメンタルヘルス対策・両立支援促進員(産業カウンセラーや社会保険労務士など)が事業場に訪問し、職場のメンタルヘルス対策に関する取り組みを無料で支援します。
また、事業場訪問以外のご相談(対面・電話・メール・オンライン)にも対応いたします。オンラインによる研修も対応可能です。
▼メンタルへルス対策支援(支援内容、申込フォームなど)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/mental
運動指導等支援について
健康で安心して働ける職場環境の形成を支援するという産業保健の観点から、運動指導等を通じた労働者の健康保持増進について取り組むため、産業保健相談員(健康運動指導士、理学療法士)による個別訪問支援等を実施しています。事業場が行う健康教育等において、是非、ご活用ください。
▼運動指導等支援(支援内容、申込フォーム)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/undou
地域産業保健センター(地域窓口)について
各地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業主や労働者を対象に、健康診断結果の意見聴取、健康相談、長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導、保健指導等の産業保健サービスを無料で行っています。
▼地域産業保健センターについて
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/cat638
<労働者健康安全機構情報>
労災疾病等医学研究普及サイトのご案内
労働者健康安全機構では、労働災害の発生状況や行政のニーズを踏まえ、労災補償政策上重要なテーマや新たな政策課題について、時宜に応じた研究に取り組んでいます。
▼労災疾病等医学研究普及サイト
https://www.research.johas.go.jp/index.html
▼「生活習慣病」について
https://www.research.johas.go.jp/seikatsu2018/index.html
▼「メンタルヘルス」について
https://www.research.johas.go.jp/mental2018/index.html
▼「アスベスト」について
https://www.research.johas.go.jp/asbesto2018/
▼「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」について
★両立支援コーディネーターマニュアルはこちら
https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1047/Default.aspx
▼「病職歴データベースを活用した研究」について
https://www.research.johas.go.jp/bs/
「両立支援コーディネーター基礎研修」について
当機構では、治療と仕事の両立支援活動推進のため「両立支援コーディネーター基礎研修」を実施しています。
この研修では、インターネット回線を利用した「動画配信研修」と「WEBライブ講習」を組み合わせた研修を行います。
動画配信による研修(20日間程度の期間において任意の時間で視聴可)をすべて受講していただいた上で、「WEBライブ講習」開催日にリアルタイム研修を受講していただくことになります。
すべてのカリキュラムを履修された方には修了証を発行します。
なお、本研修は「認定医療ソーシャルワーカーポイント」の認定ポイント対象研修(11ポイント)になります。
今年度の研修日程を当機構ホームページにて公開しています。
ご興味のある方はぜひご確認のうえ受講をご検討ください。
▼両立支援コーディネーター基礎研修はこちら
https://www.research.johas.go.jp/ryoritsucoo/
<厚生労働省情報>
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
転倒予防・腰痛予防の取組について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html
令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について(再掲)
https://www.mhlw.go.jp/stf/coolwork_20250228.html
<鹿児島労働局情報>
職場における熱中症対策の強化について
~令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます~
職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されます。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
鹿児島県内の労働災害発生状況
◯令和7年発生分(5月末)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html
最新の業種別労働災害発生状況
⇒「令和7年における業種別労働災害発生状況」をクリック
所長コラム
沖縄に比べ入梅時期が早かったにも関わらず梅雨明けは西日本全域と同日。
地球数十億年の歴史からは微変動かもしれないが、近年の気候は昔からの言い伝えが通用しない状況。熱中症警戒アラートが6月中から連日続き今夏の暑さが思いやられます。
熱中症予防策の推進は重要ですが、最早日中の野外活動は中止すべきとの思いも過ります。前駆症状すらなくても、リスクのある状態で既に作業能力は屋内外を問わず大きく落ち込んでいます。業務上のミスも増え作業起因のストレスも増大していると考えるべきです。さらに危惧されるのは、空調の多用による作業場所間の大きな気温差に伴う体調変化です。最近余り聞かなくなりましたが、いわゆるクーラー病も無視できません。また、舗装道路などからの照り返しが強い都市部では実際の気温は気象台発表より数度以上高いことも予想されます。
その昔、沖縄や奄美だけでなく鹿児島でも農村では夏場の圃場での日中作業はせずに昼休みを数時間取っていました。その頃よりも温暖化が進んでいる今日では、日中の野外作業は中止という選択肢も参考にすべきかもしれません。
尤も金融市場が24時間休み無く動いている経済システム下では「野外」という限定でも「日中作業中止」という選択はあり得ません。それでもせめて夏場には昼休みを長時間設定する、というような措置は執れないものかと淡い期待も抱きます。軽度の症状すらない状態でも、熱中症リスクのある状態での作業自体が大きな心身の健康を阻害する要因であることに十分に留意すべきです。