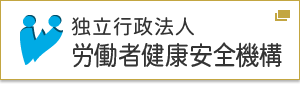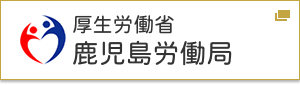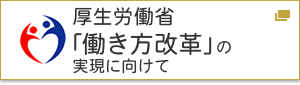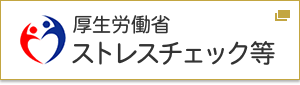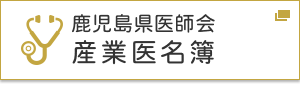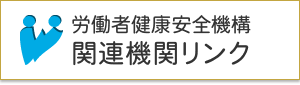メールレター 第265号
■■■sanpo■■■■■■■■■■■■■■■■■■
≪「さんぽ鹿児島」メールレター≫ 第265号(2025.4)
発行:鹿児島産業保健総合支援センター
所長 草野 健
■■■■■■■■■■■■■■■■kagoshima■■■
相談員からのメッセージ
労働生産年齢層における口腔機能ケアの課題
産業保健相談員 松下 幸誠
(担当分野:産業医学)
近年、口腔機能の重要性が広く認識され、保険適用の枠組みも整備されています。現在、口腔機能発達障害は18歳未満、口腔機能低下症は50歳以上が対象ですが、18歳から50歳の労働生産年齢層のケアが十分ではないという課題があります。
先日開催した幼児期の食育と口腔機能訓練のワークショップでは、多くの子供たちがゴム風船を膨らませることができませんでした。これは呼吸機能の問題とも言えますが、同時に口輪筋や頬筋の発達不全も影響しています。口唇閉鎖力の弱さは口呼吸を助長し、将来的な口腔機能低下のリスクを高めます。
近年、20代から口腔機能が低下し始めるケースが増えています。頬筋や頸筋の衰えは、咀嚼力や嚥下機能の低下を招き、表情や発声、姿勢にも影響を及ぼします。口腔機能の低下はフレイル(加齢に伴う虚弱状態)の進行を早めるため、若年期からの予防が重要です。
幼児期の口腔機能発達の遅れは、成長後の口腔機能低下症の早期発現につながります。さらに、食生活の乱れ、ストレスによる食いしばり、喫煙や飲酒などが加わることで、労働生産年齢層の口腔機能低下が加速する恐れがあります。
現代の食生活では、軟らかい食べ物の増加や咀嚼回数の減少が咀嚼機能の低下を招きます。これにより、消化吸収の低下だけでなく、脳の活性化や全身の健康にも影響が出ます。また、口呼吸が習慣化すると、歯並びの悪化や睡眠時無呼吸症候群のリスクも高まります。
こうした背景から、労働生産年齢層の口腔機能ケアは、生産性や生活の質(QOL)の維持に不可欠です。企業の健康管理の一環として、健康診断に口腔機能評価を組み込むことや、口腔保健の啓発活動を推進することが求められます。
現行の保険制度の年齢区分の見直しや、労働生産年齢層向けの口腔機能低下予防プログラムの導入が必要です。生涯を通じた口腔機能の維持・向上のため、すべての世代を対象とした包括的なケア体制の構築が不可欠です。
産業保健研修会のご案内(4~6月開催分 受付中!)
┏―[ 産業保健研修会の詳細・申込はこちらから ]―――――┓
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/h2335
┗――――――――――――――――――――――――――――┛
産業保健研修会の申込方法の変更に関する重要なお知らせです!
お申込み時の個人情報の管理を徹底するため、令和7年4月からFAXでのお申込みを廃止させていただくこととなりました。
お申込みフォームもしくはホームページからの手続きとなります。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
日医認定産業医(生涯研修も対象)の皆様へ重要なお知らせです。
当センターが実施する研修においてもMAMISのマイページ登録完了が必要です。
未完了の場合、単位付与ができません。
詳細は鹿児島県医師会ホームページをご覧ください。
https://www.kagoshima.med.or.jp/doctors/news/4630/
当センター主催のセミナーのご案内
当センターでは産業保健研修会以外に、事業場向けのセミナーも開催しています。
ホームページにセミナーの専用ページを開設しておりますので、産業保健活動の取組みにお役立てください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/information/seminar
■令和7年度の開催セミナーを4月中旬に公開する予定です。もうしばらくお待ちください。
お知らせ
<鹿児島産業保健総合支援センター>
産業保健に関するご質問・ご相談を受け付けています。
治療と仕事の両立支援対策やメンタルヘルス対策をはじめ、産業保健に関する様々なご質問・ご相談を受け付けています。(オンラインによる相談も可能です。)電話やFAX、ホームページからお気軽にご相談ください。
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/otoiawase
▼「さんぽセンターWebひろば」の専用ページ
https://www.johas.go.jp/Portals/0/sanpocenter/webhiroba.html
治療と仕事の両立支援について
治療と仕事の両立に関するお悩み等について、事業場関係者や産業保健スタッフ、がんなど反復・継続して治療が必要な患者(労働者)やその家族からの相談に、当センターのメンタルヘルス対策・両立支援促進員又は産業保健専門職(保健師)が相談に応じます。(オンラインによる相談も可能です。)
両立支援に関する相談、各種支援は無料です。
▼治療と仕事の両立支援(支援内容、相談窓口、申込フォームなど)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/cat765
医療機関の両立支援(出張)相談窓口につきましては、事前予約の状況等により、窓口業務を中止する可能性がありますので、当センターのホームページで事前に確認いただきますようお願いいたします。
▼「治療と仕事の両立支援」の専用ページ
https://www.ryoritsushien.johas.go.jp/blackjack/
メンタルヘルス対策支援について
当センターのメンタルヘルス対策・両立支援促進員(産業カウンセラーや社会保険労務士など)が事業場に訪問し、職場のメンタルヘルス対策に関する取り組みを無料で支援します。
また、事業場訪問以外のご相談(対面・電話・メール・オンライン)にも対応いたします。オンラインによる研修も対応可能です。
▼メンタルへルス対策支援(支援内容、申込フォームなど)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/mental
運動指導等支援について
健康で安心して働ける職場環境の形成を支援するという産業保健の観点から、運動指導等を通じた労働者の健康保持増進について取り組むため、産業保健相談員(健康運動指導士)による個別訪問支援等を実施しています。事業場が行う健康教育等において、是非、ご活用ください。
▼運動指導等支援(支援内容、申込フォーム)
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/undou
地域産業保健センター(地域窓口)について
各地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業主や労働者を対象に、健康診断結果の意見聴取、健康相談、長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導、保健指導等の産業保健サービスを無料で行っています。
▼地域産業保健センターについて
https://kagoshimas.johas.go.jp/about/about_category/cat638
全国健康保険協会鹿児島支部と協定を締結しました【令和7年3月】
当センターは、全国健康保険協会鹿児島支部と「健康づくり等の推進に向けた包括的連携協定」を締結しました。
協定内容等については、以下のとおりとなります。
(1)労働者の健康管理に関すること
(2)メンタルヘルス対策に関すること
(3)治療と仕事の両立支援に関すること
(4)健康経営の普及促進に関すること
(5)県民の健康づくりの推進に関すること
(6)その他目的を達するために必要な事項に関すること
労働者の健康増進と健康寿命の延伸を図るため、中小企業等の健康経営・健康づくりを推進してまいります。
<労働者健康安全機構情報>
労災疾病等医学研究普及サイトのご案内
労働者健康安全機構では、労働災害の発生状況や行政のニーズを踏まえ、労災補償政策上重要なテーマや新たな政策課題について、時宜に応じた研究に取り組んでいます。
▼労災疾病等医学研究普及サイト
https://www.research.johas.go.jp/index.html
▼「生活習慣病」について
https://www.research.johas.go.jp/seikatsu2018/index.html
▼「メンタルヘルス」について
https://www.research.johas.go.jp/mental2018/index.html
▼「アスベスト」について
https://www.research.johas.go.jp/asbesto2018/
▼「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」について
https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1047/Default.aspx
治療就労両立支援センター・治療就労両立支援部が中心となって、全ての疾病を対象にした治療と仕事の両立支援に取り組んでいます。
この「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」は、両立支援コーディネーターが両立支援業務を行う際に必要な基本スキルや知識に加え、事例紹介等、支援を実施する上で留意すべき事項などを記載しています。
当マニュアルは、医療従事者や企業の人事・労務担当者、産業保健スタッフの方々にも両立支援の基本的な取組方法がご理解いただけるように構成され、両立支援コーディネーター基礎研修のテキストとしても活用されています。
無料ダウンロードが可能ですので、是非ご活用ください。
★両立支援コーディネーターについて知りたい方はこちら
https://www.research.johas.go.jp/ryoritsucoo/
▼「病職歴データベースを活用した研究」について
https://www.research.johas.go.jp/bs/
<厚生労働省情報>
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
転倒予防・腰痛予防の取組について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html
令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について
今年も厚生労働省や関係団体の主唱により、キャンペーンが実施されます。
すべての職場において、「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づく基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかけ、期間中、事業者は、
- 暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること
- 熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができるための体制整備等を行うこと
- 糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうこと
など、重点的な対策の徹底を図ることとしています。
期間は、令和7年5月1日から9月30日までとし、同年4月を準備期間、7月を重点取組期間としています。
熱中症の発生を防止するためにも、積極的な取り組みをお願いいたします。
★令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001426737.pdf
★令和6年職場における熱中症による死傷災害の発生状況
(令和7年1月7日時点速報値)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001426738.pdf
<鹿児島労働局情報>
鹿児島県内の労働災害発生状況
◯令和6年発生分
◯令和7年発生分(2月末)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/jirei_toukei/toukei/saigaitoukei_jirei.html
最新の業種別労働災害発生状況
⇒「令和6年における業種別労働災害発生状況」もしくは
「令和7年における業種別労働災害発生状況」をクリック
<その他情報>
高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)から調査研究成果物のご案内
- 調査研究報告書
「職場における情報共有の課題に関する研究
-オンラインコミュニケーションの広がりなど職場環境の変化を踏まえて-」 - リーフレット
「障害者の働く職場のコミュニケーションに関するアイデア集」
高齢・障害・求職者雇用支援機構においては、令和5~6年度に実施した「職場における情報共有の課題に関する研究-オンラインコミュニケーションの広がりなど職場環境の変化を踏まえて-」の成果物として、(1)調査研究報告書及び(2)リーフレットを令和7年3月末に公表しました。ホームページからダウンロードできますので、是非ご活用ください。
(1)調査研究報告書
https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/houkoku179.html
(2)リーフレット
https://www.nivr.jeed.go.jp/research/kyouzai/kyouzai83.html
所長コラム
「桜なければのどか」とはいかず、新年度の始まりで「陋巷に人籟絶えない」今時の春です。どの職場においても新人の加入や異動・退任で構成員は多少とも変動し、陳腐な表現ですが「花相似ても人同じからず」の季節です。先月末には引っ越しの苦労の声も少なからず聞きました。只でさえ人手不足の中に運送業者の長時間労働規制の影響もあり、費用だけでなく業者手配にも随分と苦労した人が多かったようです。
先月のある会議で、ベースアップのできる企業は鹿児島のような地方には極めて少数で殆どの小企業零細企業では賃上げの原資を確保できずにいるとの声を聞きました。最賃上昇で経営はさらに厳しく、外国人労働者に頼らざるを得ない下請け企業も増加傾向とか。離職者率も増加傾向にあり、個々の従業員の業務遂行能力向上にも苦労が多い、というような切実な意見も。物価も上昇している中、世界の政治状況も混迷を深め経済動向も予測できない状況にあり、小・零細企業経営の困難さは察するに余りあります。
エネルギー資源に乏しく食糧自給率も低い我が国は人的資源以外には先進各国に伍する資源はないと言えます。その人的資源の十分な活用のためには、個々の労働生産性を向上させることが必須であり、そのためには「働き方改革」の推進は不可欠です。どのような作業現場であれ、「やりがいがある」「することがよろこびでもある」ことが肝要です。そのためにも慣例や前例に縛られず柔軟に十分な業務分析を繰り返し、「改善」を重ねることしかないと思われます。そういうような実効性のある「働き方改革」がどの職場でも着実に行なわれることを願っています。