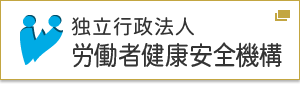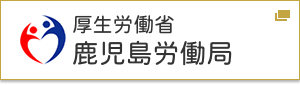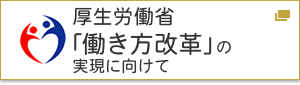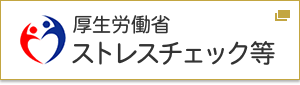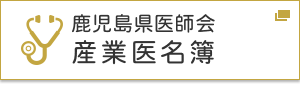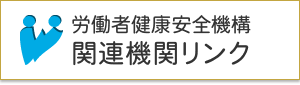22年 バックナンバー
職場の健康とエコ
特別相談員 岡村 俊彦
(担当分野:産業医学)
近年、職場でも家庭でもあらゆるところで環境問題が話題になっています。特にCO2排出に伴う地球温暖化(一部にはそんな問題はないという意見もありますが)は国際的な取り組みから個人でできる対策など、その話題を目にしない日はないほどです。
職場におけるエコ活動といえば、使っていない電灯を消す、エアコンの温度を調節する、ペーパーレスにする、といったものを思い浮かべるかもしれません。このような職場のエコ活動を産業保健の目で見てみると、意外と両者は関係しているようにも思えます。
私の職場(県立短大)には1カ所だけエレベータがあります。元々はバリアフリー対応ということで設置されたものですが、2階から1階に降りるのにもエレベータを使う、ものぐさな学生もいます。そんな学生が「ダイエットしなきゃ」とか言いながらポテトチップスを食べていたりします。エレベータの消費電力は1階分の昇降に1円もかからないそうです。しかし”塵も積もれば”ですし、健康のためにも環境のためにもエレベータは使わない、という考え方ができます。
また、パソコンの画面の明るさもけっこう健康とエコの両方に関係しています。例えば19インチの液晶画面を最大輝度の50%の明るさにすると、消費電力は約30%下がります。暗すぎる画面は作業効率に影響しますが、明るすぎる画面は眼精疲労につながります。人間工学的に適切な画面の設定は国際標準規格(ISO 13406-2など)やJIS規格(JIS Z 8513など)でも示されています。作業内容(ワープロなどのテキスト操作中心,CADなどの画像操作中心,動画視聴など)や周囲の照度なども関係してきますが、普段よりちょっと画面を暗くしてみると、健康とエコを両立できるかもしれません。
産業保健でいまだ大きな課題となっている過重労働もエコの観点から見ることができます。長時間労働をしているということは、その分、電力を使っているともいえます。広いオフィスに1人残って夜中まで残業したが、フロアの電灯をつけて、パソコンも使い、エアコンもかけて、では電気代もかさみ、健康にも悪いということになってしまいます。「長時間労働は自分の健康だけでなく地球環境も破壊する」と考えると、過重労働の問題も少しは解決していくかもしれません。
このように見ていくと、職場でのちょっとしたエコ活動は意外と労働者の健康にとってもプラスになり、さらに経費削減にもつながっていく、といういいことずくめに思えてきます。この原稿を書いているうちに外が暗くなってしまいました。そろそろパソコンの電源を切って、車は職場に置いてバスで帰りましょうか。私なりのエコ活動です。赤提灯さえ目に入らなければ、健康にもいいはずです。
平成22年12月 第714号 掲載
「産業保健の話題(第112回)」
ポピュレーションアプローチ
基幹相談員 小田原 努
(担当分野:産業医学)
今年の3月に「定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組について」の基発がでました。この基発とは厚生労働省労働基準局長名で発する通達で、役所内部の訓令を意味し労働行政を拘束するものですが、結果として一般国民も拘束されるものです。
今回の内容は、定期健康診断の有所見率が50%を超え、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災支給件数も増加していることから、脳・心臓疾患の発生防止の徹底を図ろうとするものです。
脳・心臓疾患のハイリスク者が長時間労働を行い、自然の経過が加速されて、疾病を発症するという理論が根拠となっての今回の取組で、血中脂質検査、血圧、血糖検査、尿中の糖検査及び心電図検査または定期健康診断の検査項目全体の有所見率が全国平均の有所見率より高い場合、あるいはその増加率が全国平均の増加率より高い事業所に関しては、労働局や労働基準監督署は事業者の取組事項に関して、重点的に周知啓発、要請などを指導することとなっています。
産業医としては、定期健康診断の有所見者に対しては保健指導等を行うこととなっていますが、これはハイリスク者に対するハイリスクアプローチです。
当然疾病の早期の段階から介入することは疾病の自然経過を遅らせる上で効果的なアプローチではありますが、事業所で脳心事案が発生するのは、比較的軽度な検査値異常の方が多く、例えば事業者から本当に血圧が高いと脳・心臓疾患を起こす可能性が高いのですかとはよく聞かれる質問です。
ただこれは、血圧の分布を考えると分かることで、異常高血圧の方は、リスクは高いものの実際の人数はわずかです。
軽症高血圧の方は、リスクは低いものの実際の人数は多く、実際の疾病の発症者が「その血圧での発症リスク」×「その血圧帯の人数」ですので、軽症高血圧の方の脳・心疾患の発症人数が多くなることは理解できます。
特に血圧は、診察室では正常であるものの、診察室以外で高い仮面高血圧や職場でのみ高い職場高血圧の方も多いために、高血圧の値だけで一律に残業制限などをつけようという対策では効果は限定的です。
業務に起因する疾病を防ぐにはまずは作業環境を整えること(例えば長時間労働は有害要因なので、まずは時間外勤務を減らす)ですが、それとともに、健康管理を行いハイリスク者には重点的にアプローチするとともに、食堂に減塩ランチを用意する、禁煙活動を会社で推進する等、皆の血圧をさげるポピュレーションアプローチを取ることが、定期健康診断の有所見率を減らす抜本的な対策になると思われます。
平成22年11月 第713号 掲載
「産業保健の話題(第111回)」
じん肺健康診断に関係する一部の法律が改正されました
特別相談員 牧野 正興
(担当分野:産業医学)
昭和35年にじん肺法が制定されて以来50年余りが経過しています。粉塵作業に従事する労働者には、昭和53年基発第250号労働省労働基準局長通達により「じん肺診査ハンドブック」(昭和54年改訂)に記載された内容を基本とした「じん肺健康診断」がこれまでの永年にわたって行われてきたところであります。
これらじん肺健康診断などの取り組みにより、昭和55年度に認定された新規じん肺患者数は6842人であったのが、30年後の平成20年度の全国集計ではわずか244人に激減しています。
近年、医学の進歩はめざましく「じん肺ハンドブック」に採用されている検査法やそれらの判断基準が旧態化してきていることも事実であります。また、じん肺についての新たな医学的知見も蓄積されてきていることより、必要な見直しを行うための検討会が開かれその内容が本年5月、報告書として答申され7月1日、直ちに改正法として公布/施行されました。
「主な見直しの内容」
1). 肺機能検査で用いる指標の追加等( %1秒量、PaO2の追加、V25/身長の削除 )
2). 各指標における基準値についての見直し ( 日本呼吸器学会における年齢、性別、身長により予測される正常値を用いた判定 )
3). 喫煙歴については、健康診断結果報告書における喫煙歴の記載欄の追加 以上の3項目が主要な改正点であります。
従って、肺機能検査において、%肺活量においての肺活量の正常予測値、また1秒率および今回追加された%1秒量における正常予測値の算出に当たっては、いずれも2001年に日本呼吸器学会が提案した予測式が適用されることになりました。
じん肺の進行の把握、およびじん肺管理区分の決定に当たっては、じん肺による肺機能障害が著しいか否かを判断する必要がある訳ですが、1次検査(スパイロメトリー検査、フローボリューム曲線による検査)でそれらの検査値が一定程度低下している場合には2次検査として、動脈血ガス分析が行われます。低酸素血症の指標である動脈血酸素分圧(PaO2)が60 Torr以下であることが「著しい肺機能障害と判定する」基準値として初めて数値が明記されました。
この60 Torrという数値は、高度慢性呼吸不全症例に対して保険診療で適用される在宅酸素療法(HOT)導入時の数値と一致しており理にかなったものであります。PaO2 は他の肺機能検査と異なり、人為的な作為が及び難く、客観的に適切な判断が得られる最も信頼できる検査と考えられています。某公立病院ではじん肺健康診断結果証明書を労働局へ提出する際には、法的には要請されてはいないにもかかわらず、肺機能検査時の出力伝票(検査報告書)のコピーを敢えて添付しているとのことでした。
動脈血ガス分析では更にガス交換障害の指標である肺胞気動脈血酸素分圧較差(AaDO2)がハンドブックに示されている限界値を超えることも「著しい肺機能障害と判定する」とされています。
じん肺の管理区分決定申請のための健診では、胸部X線写真(アナログ、CR、DR)があくまでも基本とされますが、近年、胸部CT検査は日常診療においてルーチンに実施されているはずですので、参考資料として申請時にはCTフイルムも添付して提出されるのが望ましいものと考えられます。診査する立場を推測するならば、可及的多くの判断材料が添付されている方がより容易に正確な管理区分決定がなされることだろうと思われます。肺機能検査によって得られた数値が著しい肺機能障害に相当する基準値であると,鬼の首を取ったように機械的に当てはめての判断を記載することなく、粉塵作業歴、既往歴および過去の健康診断の結果、X線写真、胸部の自覚症や臨床所見などを総合的に評価して判断した結果をもってじん肺健康診断結果証明書を完成させて下さい。
平成22年10月 第712号 掲載
「産業保健の話題(第110回)」
一酸化炭素中毒(CO中毒)の予防
基幹相談員 竹内 亨
(担当分野:産業医学)
COは古くから人に重篤な中毒を引き起こす有毒ガスであることが知られており、多くの人がその危険性を認識している。
しかしCOの毒作用で亡くなる人が毎年数千人(平成20年は4017人)に上っている。産業現場でも毎年CO中毒が発生している。平成21年1月には鹿児島県内の高等学校でもCO中毒事故が立て続けに2件発生した。COによる中毒事故をなぜ防げないか、どうすれば予防できるかを考えてみたい。
COはヘモグロビンとの親和性が酸素より200倍以上も高く、血液の酸素運搬能を低下させ、組織の低酸素を引き起こす。その結果多くの酸素を必要とする臓器、特に脳や心臓に障害を引き起こす。
しかしCO中毒には特徴的な症状がなく、感冒様や胃腸炎様の症状が発生する。 一方はCOは有機物が燃焼する過程で必ず発生する。しかしCOには刺激性や臭気、色はなく、COが発生していても我々は感知できない。
我々がよく目にする、物質が燃焼している時に発生する青い炎は、COが燃焼している色であると言われている。赤い炎の時にはCOが十分に燃焼されず、ガスとして周囲に漏れ出ているのかも知れない。
COは燃焼により発生し、我々はその発生や蓄積を感知できず、更にCO中毒に陥っていても気づかない状態では、CO中毒事故が無くならないのは当然かも知れない。
換気をすればCO中毒事故を予防できるかといば、そうとも限らない。前述の高等学校でのCO中毒事故の1件は調理実習中に発生したが、CO中毒事故発生時に換気扇は回っていた。
経済産業省は、換気扇を稼働させていたが、窓やドアを閉め切っていたため室内が陰圧になり、自然排気で屋外に放出されるべき暖房機器のCOが室内に逆流し、中毒事故が発生したと推定している。
CO中毒事故を予防することは不可能だろうか?COの発生や蓄積に気づけば、予防できると思う。欧米ではCO警報器が広く使われているようである。
CO中毒の多く、特に重篤なCO中毒は、CO警報器が設置されていない場所で発生していると報告されている。
CO警報器を設置すれば、COの蓄積に気づくことができ、CO中毒事故を未然に防ぐことができると感じる。CO警報器はネットで検索すると2万円程度で販売されている。警報音の従業員への周知、適切な場所への設置、センサーや電池には寿命があるためその管理を行えば、CO中毒事故の予防に威力を発揮するものと感じる。
特に厨房のような大型の燃焼機器を稼働させる職場、荷物の積み下ろしを行う屋内車庫、内燃機関を閉所に持ち込む作業等ではCO警報器の設置や携帯は必須と思う。CO中毒事故の予防は意外にシンプルかも知れない。なお筆者はCO警報器の製造販売企業からの援助は一切受けていない。
より詳しい内容は産業衛生学雑誌2009; 51: 71–73に掲載しており、
からフリーでダウンロードできるので、ご参考にしていただければ幸いである。
平成22年9月 第711号 掲載
「産業保健の話題(第109回)」
「ケンシン」について思うこと
特別相談員 草野 健
(担当分野:産業医学)
「ケンシン」には「検診」と「健診」という二つの漢字が存在する。この二つは似ているが、その意義や目的は同じではない。残念なのは一部のメディアや関係者に混同して用いる者がいることである。
「検診」は英語ではscreeningであり、その意味するところは「篩(ふる)い分け」である。医学的には2次予防、つまり早期発見・早期治療のために標的疾患を無症状のうちに拾い上げる方法である。
検診の典型的なものとしては、昔ながらの結核検診があり、最近では各種のがん検診がある。がん検診の目的は、対象集団の標的がんによる死亡率を減少させることであり、救命できる時期に発見することであって、微小がんの発見が目的ではないことにも留意することが必要である。
「検診」は飽くまでも集団を対象としたものであり、個々人の死亡リスクを減じることを第一義とはしない。
一方、「健診」は英語ではhealth checkまたはhealth examinationであり、対象者個々人の健康状態をチェックし健康リスク(健康破壊要因)を明確にするものである。
「検診」は、標的疾患の疑い者をピックアップして診療の場に送り込めば、精検と必要に応じての治療およびその後の予後追跡でとりあえず完結する活動である。
しかし「健診」は、健康状態を診断した後、必要な診療を提供するだけでなく、その健康疎外要因を除去することまでが要求される。
つまり「健診」は、一次予防と二次予防を併せて行う活動であり、集団対象の「検診」と異なり個人と集団双方の視点で行うことが必要とされる活動である。
ところで、「健診」は略語であるが、正式には健康診断または健康診査である。面白いことに、健診に関わる学会では健康診断を用いるが、厚生労働省でも旧厚生省系では健康診査を用い、決して健康診断とは使わない。
一方、旧労働省系では逆に健康診査ではなく一貫して健康診断を用いている。労働安全衛生法では、事業所に対して各種の「健康診断」を実施することを義務付けている。
労働者の健康を維持・増進するためには健康疎外要因を除去すること、とりわけ労働によって健康が損なわれることがないようにすることが必要であるが、そのためには二次予防の「検診」ではなく一次予防の「健診」が必要となる。
「老人保健法」や「がん対策基本法」でがん検診が法制化されても、事業主にはがん検診の実施は義務化はされていない(自主的実施は勧められている)が、これは「検診」が二次予防であり、労働環境改善に役立つ一次予防ではないことから、当然ともいえる。
ともあれ、事業所健診には各種の健診があるが、いずれも疾患の早期発見だけでなく、むしろ健康リスクを明確にし、その除去方策を立てることが「健診」の目的であることを忘れてはならない。
平成22年8月 第710号 掲載
「産業保健の話題(第108回)」
裁判員のメンタルヘルス
基幹相談員 久留 一郎
(担当分野:カウンセリング)
朝日新聞(平成22年5月20日付)による裁判員裁判のアンケートから「語れぬ重荷~心に体に~」という見出しで、裁判員経験者の心理的ストレスや精神的負担を取り上げている。
また、同紙(5月7日付)の記事では、裁判員だった女性が「裁判を機に体調を崩し、仕事を辞めた」という事例を取り上げている。このケースについて、精神科医のコメントによれば「心的外傷後ストレス障害(PTSD)などのトラウマ反応を強く起こしている」と述べている。
昨年、5月21日から刑事裁判における裁判員制度がスタートし、1年が経過したところである。南日本新聞(平成21年6月14日付)の「時論」に「裁判員のメンタルヘルスをめぐって」という筆者の記事が掲載された。裁判員の被るストレスやトラウマについての危機介入や予防について述べたもの(上記のような事例を予測した内容)であり、一部引用し、紹介させていただきたい。
「裁判官」というプロと違い、「裁判員」は自己の意志による選択でなく、偶然選ばれたというアマチュアの存在である。刑事事件の内容によってはきわめて凄惨な事件や事故の状況を見聞することになり、裁判員の中には間接的なトラウマを被り(二次受傷)、心のケアが必要な場合も出てくる危険性が予測される。
たとえば、裁判員自身やその家族、身内が刑事裁判の内容とよく似た経験(事件や事故の被害者の経験)などがあると、フラッシュバックという症状が蘇ることもある。予め裁判員の「再体験」を煽らないような方策や「回避」していたいことなどを聴取し、フラッシュバックを予防することが必要になる。
筆者は、極めて惨い犯罪被害者の心理面接を担当したカウンセラーの二次受傷を予防するため、必要に応じてそのカウンセラーの面接をする場合がある。いわば「二重構造」のカウンセリングともいえる。これも支援する側がストレスに苛まれ、トラウマを被らないための予防的方法である。
裁判員の場合、守秘義務の責任だけを強調されすぎると、抑圧された感情を解放することも不可能に思われる。しかし、そのような事態を危惧して、最高裁判所では、裁判員のためのカウンセリングのネットワークを提案しており、必要に応じて外部の専門機関に委託するという。
「開かれた」裁判員の制度が発展していくには、裁判員のメンタルヘルスについての明確な説明責任が問われているように思われる。個人の意志とは全く無関係に選ばれ、罰則付きの守秘義務を背負わされる裁判員の人権を保護するシステムを構築する必要がある。裁判員にとって、「安定した心理的状況」で裁判に臨むことのできる制度を強く願わずにはおれない。
裁判員に選ばれた人間にとって、メンタルヘルス・システムがきちんと構築され、安心・安全の世界が満たされるとき、はじめて、公正な、自己決定的「評議」がなされる。不安と懐疑の心理的状況では、決定することへのためらいや戸惑いを煽り、逆に、裁判員という「隠れた被害者」を生み出す危険性がある。
平成22年7月 第709号 掲載
「産業保健の話題(第107回)」
ウツ病臨床、扉のこちら側「ウツ」は風邪を超えた、か?
特別相談員 大迫 政智
(担当分野:メンタルヘルス)
「風邪くらいで休むんじゃない」という上司も、この冬あたりから急激に減ってきた。新型インフルエンザ騒ぎの影響であろう。それでも、「そんなものは気合いで乗り切れ」という上司も未だ少なくないようではある。こちらは不況による人減らしの影響であろうか。
一方、「ウツならしっかり休め」と言う上司は、十年一昔というべきか、確実に増えてきているようである。
初診時にせっかちに「休養が大切だから」と休職診断書をいきなり求める人が出現している。問えば、上司からそうするように言われて来院した、という。
ウツ病でクリニックを受診することに、抵抗が薄れてきたことと捉えれば、望ましいことといえるだろう。また、「ウツ病は気合いだけでは乗り切れない」という事実が、世間で認識されてきた証左ともいえるであろう。
しかし、休養するように命じられて、「このまま首になったらどうしよう」と疑うこともなく、診断書を希望して受診するという素直な行動は、かつての教科書に載っていた典型的な「ウツ状態」の症状といって良いのだろうか。「ていの良い人員削減(肩たたき)の第一歩じゃないだろうか」と心に浮かんでも、今の時代、即座に被害妄想とは言えないであろうに。
他方、初診医が「ウツ病」と簡単に診断できるように、症状をいくつも丁寧に説明してくれる親切なウツ患者も増えた。インターネットなどで「ウツ状態のチェックリスト」の点数をクリアしているという訳だ。だが、何か違和感がある。言葉の深みというのか、言葉の現実感というのか、初診医の耳には来院者の「心の顔の苦渋の皺」が響いてこないのだ。これは、チェックリスト方式の持つ特徴なのだろうか。
そもそも「ウツ状態」の人は、いかに相手が医師とはいえ、自らそんなに仔細に症状を語るものだったのだろうか。 「ウツ病の三主徴」を問われていた頃の大学病院精神科外来では、こんなウツ状態はまずお目にかからなかったように思う。もし出会ったとしても、これをウツ病と診断しようものなら多分、大目玉を食らっていたような気もする。時代と共に変化してきているウツ病像に、次第に外来医の目が慣れて、そう診断するようになってきているのか。あるいは目が慣れた末の、それは誤診とは言えないのか。
精神科医は悩みながら外来の椅子で今日も来院者に耳を傾けている。(この苦悩など何処吹く風と、クリニック精神療法点数は下がりゆくが、まあそれはそれとして)
平成22年6月 第708号 掲載
「産業保健の話題(第106回)」
「脳・心臓疾患及び精神障害に係る労災補償状況(平成20年度)」の報告について
基幹相談員 前田 雅人
(担当分野:産業医学)
「産業保健の話題」の原稿依頼がいつもこの時期に回ってきます。私が担当している3月の産業医研修セミナーのタイトルが「職場で起こった循環器疾患」であり、厚生労働省のホームページを見る機会が多いことから、ここ数年は「脳・心臓疾患及び精神障害に係る労災補償状況」の報告をさせていただいております。今回も平成21年6月に厚生労働省から発表された資料について報告いたします。
一般に作業現場での外傷事故であればすぐ労災補償を思いつくのですが、外傷でない「脳・心臓疾患」の場合、なかなか判断し難いケースが多いかと思います。また労災の認定する「脳・心臓疾患」は対象疾患が決まっており、脳血管疾患なら脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症であり、虚血性心疾患なら心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤です。これらの疾患は血管病変が自然経過によって悪化し発症する、いわゆる私病増悪型疾患であると考えられるわけですが、労災認定の折には業務により明らかな過重負荷が加わることで、血管病変が自然経過を越えて著しく増悪し発症したとして判断される必要があります。
さて平成20年度の「脳・心臓疾患」についてですが、請求件数をみたところ、889件と前年度より42件(4.5%)減少していました。年々増加の一途をたどっていた請求件数がなぜ減少に転じたのかは不明です。一方請求に対する支給件数も377件と昨年よりも15件(3.8%)減少していました。支給決定件数の業種別では「運輸業」が最も多く(99件、26.3%)、次いで「卸売・小売業」(62件、16.4%)であり、職種別では「運輸・通信従事者」(98件、26%)、「専門的・技術的職業従事者」(59件、15.6%)の順でした。
年齢別では50~59歳の請求件数が最も多く(327件、うち死亡102件)、次いで40~49歳(217件、うち死亡89件)でしたが、支給が認められたのは50~59歳(142件、うち死亡58件)、40~49歳(116件、うち死亡48件)と厳しく、全請求(889件)に対して、支給決定は377件(42.4%)でした。
鹿児島県については、平成20年度の脳血管疾患の請求は2件、支給は3件(前年度以前請求分を含む)、虚血性心疾患等の請求は4件、支給は2件でした。
一方うつ病や仕事上のストレスなどが原因の「精神障害等の労災補償状況」についてみると、請求は927件であり、前年度から25件(2.6%)減少していました。
支給件数については269件と前年度より1件(0.4%)の増加でした。「脳・心臓疾患」と同様、前年度までの明らかな増加傾向は収まっているようです。
支給件数の業種別では、「製造業」(50件、18.6%)が最も多く、次いで「卸売・小売業」(48件、17.8%)の順であり、職種別では「専門的・技術的職業従事者」(69件、25.7%)、「生産工程・労務作業者」(51件、19%)の順でした。年齢別では30~39歳の請求件数が最も多く(303件、うち自殺31件)、40~49歳(239件、うち自殺44件)の順でしたが、支給が認められたのは30~39歳(74件、うち自殺11件)、20~29歳(70件、うち自殺10件)であり、全請求(927件)に対して、支給は269件(29%)でした。前述の「脳・心臓疾患」と比べ、より若年層に問題があり、また業種、職種の順位も異なるものでした。
鹿児島県については、精神障害等の請求は9件(うち自殺1件)、支給は1件でした。 長く続く不況が「脳・心臓疾患及び精神障害に係る労災補償状況」におよぼす影響について、注意して見ていきたいと思います。
平成22年5月 第707号 掲載
「産業保健の話題(第105回)」
「トラウマはなぜ蘇る?」
基幹相談員 久留 一郎
(担当分野:カウンセリング)
DSM-Ⅳ(APA)においては「トラウマとなる出来事」について次のように記述されている。
- 本人が、危うく死ぬ(殺される)、または重症を負うような危機的な出来事を実際に体験し、目撃し、直面すること。
- または、自分や他人の身体の保全に迫る出来事を体験し、目撃し、直面すること。
- さらに、出来事を体験した本人の反応は、強い恐怖、無力感や戦慄に関するもの。
すなわち、このような「異常な体験」を被った場合、誰もが「正常(自然)な反応」として「トラウマ」反応を表現することになる。虐待やDV,パワハラやセクハラなども「異常な体験」であり、「避けがたく、逃れようのない」場合、トラウマを被ることになる。
トラウマを被った人間はしばしば過去の自分の「トラウマ体験を再現する」ことがある。他者との人間関係の中で再現する場合や自分自身に向けて自傷行為などの形で再現する場合などがそうである。
- トラウマ体験のプロセスにおいて、「侵入反応」と「マヒ反応」という二相性があることが知られている。
- 「侵入反応」は活動性の亢進、怒りの爆発、悪夢などの様式で出現し、外傷場面を想起させるような「再現」をする。
- 「マヒ反応」は感情の収縮、社会的孤立、失感情、疎隔感、解離現象などの様式で出現し、反復する外傷場面の侵入性想起からの「防御」の機制と考えられる。
- トラウマ体験のプロセスにおいて、フラッシュバック(よみがえり)現象を伴うことが知られている。
フラッシュバック(Flash-back)とは、過去の忌まわしい出来事や体験があたかも現実のようによみがえってくる現象である。「あの時、あそこで、体験したこと」が、視覚的なイメージ、悲鳴や様々な音、臭い、身体が受けた体感、そして強い恐怖心や無力感などを伴い、蘇ってくる現象をいう。トラウマの「消化吸収」の機制と考えられる。
このような体験を被った被害者には、治まりのつかないトラウマが噴き出し、蘇ってくるが、このことを「正常(自然)な反応」として本人に伝えることが大切である。 トラウマのメンタルヘルスにおいては、トラウマを被った人間はその反応を「異常な反応」として受けとり、二重に苦悩することが多い。そのため、支援する側は「正常な反応」であることを被害者に伝え、理解してもらうこと(ノーマライゼーション)がきわめて重要である。
引用文献
久留一郎(2010)近刊「危機における心理支援学~トラウマとは、トラウマ体験の症状~」 (日本心理臨床学会編)
平成22年4月 第706号 掲載
「産業保健の話題(第104回)」
働く人にみられるシンドローム
基幹相談員 長友 医継
(担当分野:メンタルヘルス)
労働者は職場で様々なストレッサーにさらされます。このような状況に適応できなくなり発症するストレス関連疾患が適応障害といわれるものです。
適応障害は国際的な診断基準(DSM-Ⅳ)では、
- 不安気分を伴うもの
- 抑うつ気分を伴うもの
- 行為の障害を伴うもの
- 情動と行為の混合した障害を伴うもの
- 身体的愁訴を伴うもの
- 引きこもりを伴うもの
に分類されます。
一方、小此木らは、職場でみられる適応障害などを労働者の性格や職場環境などの状況と関連させて、「働く人にみられるシンドローム」として紹介しています(こころを診る、中災防、1995)。これらは産業精神保健の対場からは理解しやすいものですので、幾つかを紹介してみたいと思います。
1.仕事依存症候群
私生活の殆どを犠牲にして、仕事に打ち込んでいる状態です。ワーカホリック(仕事中毒症)ともいわれます。 労働者は仕事にのめり込まず、休息を取り入れた生活が大切であることはいうまでもありませんが、ワーク・ライフ・バランスとしては、仕事:5割、家庭:3割そして余暇:2割が推奨されています(夏目)。
2.ブルーマンデー症候群
月曜日の心身の不調を指します。日曜日の夜になると、翌日の月曜日の仕事ことを考え始め不眠などが生じ、月曜日の朝に調子を崩してしまった状態です。 「サザエさん症候群」も同様な状態を現す用語です。日曜日の午後6時30分から放映される「サザエさん」は、楽しいアニメであり、本来なら笑えるはずのものです。
しかし、その頃に、翌日からの仕事などを考え出し、気分が落ち込み、楽しいはずの「サザエさん」を見ても、素直に笑えない状態をいいます。
3.朝刊症候群
朝出勤前や会社で朝刊を読んでいた人が、新聞を読みたくなくなったり、読んでも頭に入らなくなったりする状態を指します(笠原)。働く人におけるうつ病の初期症状の一つといわれています。
4.サンドイッチ症候群
上司と部下の板ばさみになってしまい、心身の不調を来たした中間管理職を指します。 さらに、「新サンドイッチ症候群」という用語もあり、会社と家族の板ばさみになる状態をいいます。会社と家族のどちらかも疎外され、孤独を感じますので、サンドイッチ症候群よりも深刻であるといわれています。
5.燃え尽き症候群
自分自身にとって実現不可能な期待を自らに課し、それを達成するために頑張りすぎ、疲れ果てたり、欲求不満に陥った状態をいいます。対人保健・福祉サービス業の専門職である看護職や介護職に出現頻度が高いものです。 本症候群は、脱人格化、情緒的消耗感そして個人的達成感の3つの因子から成り立ちます。以下にそれぞれの具体的な症状を記します。
- 脱人格化:同僚や患者と何も話したくなくなる、同僚や患者の顔を見るのも嫌になる、仕事の結果はどうでもよいと思う、など。
- 情緒的消耗感:身体も気持ちも疲れ果てたと感じる、一日の仕事が終わると「やっと終わった」と思う、こんな仕事はもうやめたいと思う、など。
- 個人的達成感:仕事が楽しくなく、時間がたつのが遅い、この仕事は自分の性分にあっていないと思う、今の仕事に喜びを感じない、など。
このうち、脱人格化の症状があるため、燃え尽き症候群を呈した人は、対象者に対して虐待を行う危険性もあります。
6.上昇停止症候群
同僚や後輩が先に昇進したり、高い給料をもらっていることを知ることで、自分のキャリアの限界を悟り、やる気をなくしたり、無気力になったりする状態です。挫折無く順風満帆に出世してきた中高年の男性が陥りやすいと言われています。
7.スーパーウーマン症候群
仕事も家庭も完璧に全てをこなそうとする女性、即ち、職場では男性と対等に仕事をし、家庭では良妻賢母であろうとする女性が罹りやすい状態です。
8.テクノ依存症、テクノ不安症
テクノ依存症は、インターネットに没頭し、それがないと気がすまない状態です。「アルコール依存症」や「ギャンブル依存症」などとともに、職場でみられる依存症の一つです。
テクノ不安症は、OA機器操作が苦手であり、これを長時間行うことで、眼精疲労、肩凝りなどの様々な身体症状や抑うつ、不安感などの精神症状が出現するものをいいます。
これらの症候群は、正確には医学用語ではありません。しかし、職場におけるストレッサーにより心身の不調を来たした患者に、発症の状況や対応の仕方を説明する際には、有用な用語であると思われます。
平成22年3月 第705号 掲載
「産業保健の話題(第103回)」
復職支援
特別相談員 小田原 努
(担当分野:産業医学)
平成21年3月に「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が改訂されました。主な改訂点として、あらかじめ職場復帰支援の諸規定を作成するとともに労働者に周知することや、主治医との連携の重視、試し出勤制度のルール化、教育研修の充実化などがありますが、基本的な考え方は旧手引きを踏襲しています。
復職してもすぐ休職してしまう、日常生活に支障ない程度回復しても業務遂行能力まで回復したと判断できず、職場の受け入れに躊躇してしまうなどの復職困難事例が増えていることも改訂の一因と考えられますが、丁寧に手引きのステップを踏むことで、復職時の産業医としての対応もだいぶ迷いなく行えると思います。
復職のステップとして、第一ステップは疾病休業開始及び休業中のケア、第二ステップは主治医による復職可能の判断、第三ステップは職場復帰の可否及び職場復帰支援プランの作成、第四ステップは最終的な職場復帰の決定、第五ステップは職場復帰後のフォローアップですが、今回は第五ステップ職場復帰後のフォローアップの注意点を述べてみたいと思います。
心の病による休職の大半を占めるうつ状態や職場不適応の原因は職場要因や個人要因がいくつか重なったケースが多いのですが、今まで職場に適応していた方が配転や上司が変わったなどの明らかな職場要因がきっかけに不調となった場合、職場環境を調整してあげることが再発を防ぐ上で大事です。もちろん個人の認知や考え方に働きかけることも必要ですが、当面の目標は再度休職とならないようにすることが大事で、休職を繰り返すと職場復帰がかなり難しくなっていきます。
復職しても3カ月ほどは朝起きて出社し仕事して帰って寝るという、最低限の生活パターンをきちんと行うことが大事であることを職場にも本人にも説明します。もう治ったと職場の方の誤解を解くことと同時に稀に休職中の遅れを取り戻そうと頑張りすぎることを防ぐねらいもあります。時々躁転してしまい1カ月ほどで再休職になるケースもありますので、気になる場合は2週間後ぐらいにフォローの面接を行うようにしています。職場の上司にも退勤の時間がきたら本人に帰るように声かけする等目立たないように保護してもらうことをお願いします。
復職後1,2カ月は1日や2日休んでしまうのは一般的と説明してあげると本人も安心するようです。復職直後は残業制限や休日出勤禁止などの制限を設ける場合が多いのですが、3か月もたつと職場側も制限が続く事にしびれをきらしてきますし、本人も周囲の目を気にしたりして仕事をしづらくなってくる場合があります。3カ月で制限を解除してしまうのは早すぎる場合が多いのですが、場合によっては一部制限を解除したり、あと3カ月後に制限を一部解除できるかもしれないと見通しを伝えてあげると職場も納得してくれます。
大切なことはあわてず目標を下げて臨むことと、産業医としては職場に産業医意見書を適時発行して上司が変わっても職場の対応が継続するように注意することです。
平成22年2月 第704号 掲載
「産業保健の話題(第102回)」
うつ病・うつ状態の時代的変容
基幹相談員 福迫 博
(担当分野:メンタルヘルス)
近年、うつ病に関しては、精神障害という偏見が残っている地域や世代が一部存在するが、マスメディアで取り上げられる機会が増え、敷居が低くなり心療内科・精神科クリニック、精神科病院を受診する患者数が増加している。
典型的なうつ病は、「メランコリー親和型」に代表される、真面目、几帳面、融通が利かず、秩序を重んじるといった性格傾向の人が、様々なストレスを負荷されることによって引き起こされる心身の諸症状を呈する病であり、その経過や治療法が初診時に描けるケースがほとんどである。
すなわち、抗うつ薬と休養が主たる治療法であり、数カ月~1年間程度の治療期間であるなど、患者や家族に比較的画一的な説明をすれば8割~9割の患者が寛解に至る一群である。診立てがしっかりしていれば、入院治療に導入し自殺予防もできる可能性が高い。
一方で、「うつ病」という概念が拡大使用され治療現場や職場で混乱が見られるのも確かであり、2年前の日本精神神経学会において、このような現況に関するシンポジウムが開催された。私のクリニックを受診する患者の1/4程度が紹介状を持参するが、プライマリケア医や関東、関西方面のメンタルクリニックから紹介されて受診する患者の診断名として多いのが、適応障害とうつ状態である。うつ病という診断名を記載されている患者は少数派である。
適応障害については、ICD‐10では個人の素因が強く関与すると定義されているが、実際的には環境的要因の関与が大きい人が多くみられ、職場や家庭環境を変化させることで軽快することも多く、抗うつ薬や睡眠薬は補助的に使用している。慢性・遷延化した本格的うつ病に陥らないように底支えとして服用してもらっている患者もおり、それなりに効果はあると考えている。
しかし、最近受診する「うつ状態」を呈する患者の中には、他罰的で非協調的、自己中心的で自尊心が傷つきやすく、それでいて他者を見下す傾向があるといった特性を有する「うつ状態」の患者の割合が高くなっている。このような患者の特徴としては、人間関係において勝ち負けにこだわる傾向、共感性が乏しく他者に対して狭量、容易に人に打ち解けないなどがあげられる。対人関係上でも大きな障害を示す傾向があるため、職場における対応も苦慮することが多い。
症状的には、抑うつ症状と自己評価の低下、自己不信と他者不信を持ち、摂食障害、職場不適応、対人関係困難、不潔恐怖症(強迫性障害)、社会的ひきこもり、DVなどを呈する。薬物療法は奏功せず、治療関係も不安定でドクターショッピングしている患者も多いと思われる。ディスチミア親和型うつ病とも呼ばれているが、境界性人格障害や自己愛性人格障害がベース(あるいは併存)である患者が多く、治療は難渋する。そして、このような患者にSSRIやSNRIを使用すると「アクチベーション (抗うつ薬の投与開始初期や増量時などに見られる精神行動症候群であるが、その定義はまだ確立していない)」が惹起されやすい傾向があると、昨年のうつ病学会である程度の見解が示された。
このような実情を考慮しないで、マスメディアによる抗うつ薬の使用に関する不快ともとれるバッシング(反省すべき点もあろうが)があると、治療する側としては憤りを覚えることもある。ここ1年間で、職場の上司が自己愛性人格障害(的)であるため、うつ病に罹患した患者を2例経験した。産業医や事業場内産業保健スタッフの方々もこのような事例に多く遭遇するようになり、それなりの対応がなされているように感じている。医療の現場においても同様の傾向が見られるのではと危惧しつつ記述した次第である。
平成22年1月 第703号 掲載
「産業保健の話題(第101回)」